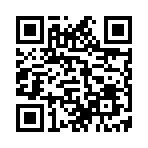2023年01月30日
2019年02月05日
勝敗を度外視して美学にこだわる指導者に、岡田武史と小野剛が覚える違和感
こちらは『ジュニアサッカーを応援しよう!』から、、
https://jr-soccer.jp/2019/02/02/post109014/
@ーーーーーーーーーーーーー
【勝敗を度外視して美学にこだわる指導者に、岡田武史と小野剛が覚える違和感】
必死でやって負けても問題ない
岡田 俺は人を批判しない。いろんな人がいていいと思う。みんな同じサッカーだったら面白くない。
小野 みんなが勝ちたいと思って必死にやってきた結果、国民性とかに合ったスタイルが出てくるという考え方は、本当にそうかもしれないですね。最初に戦略があって、それを目指した結果ではなく、勝ちたいと思って努力した結果、スタイルが出てきた。最近、そういうのを「〇〇スクール」という言葉で表現していますね。
岡田 チーム作りと采配の2つがあると、日本人の指導者はチーム作りに美学を感じる人が多い。采配で勝つのは邪道だと。両方大事なんだけど。最後にパワープレーを仕掛けて勝つと、最初からパワープレーやればいいじゃないかという極論が出てくる。いやいや、それはリスクが大き過ぎるだろうと。もちろん、自分のスタイルだけにこだわって、勝敗を度外視してはいけない。絶対に勝つという気持ちを持たないで、スタイルにこだわって、負けてもいいと言い始めると、サッカーは進歩しないと思う。
小野 そこに美学を求めると、確かに進歩がありませんね。
岡田 ポリシーや哲学があるのは当たり前。それで、勝たなきゃいけない。
小野 勝利至上主義に関する賛否の議論も、方法論の話だと思います。その年代以外では通用しない方法論で勝つのはどうかとは思いますけど、とにかく目の前の試合に勝ちたいという気持ちを忘れてはいけない。
岡田 そのとおり。小学生年代ならデカい子を前に置いて、ボーンと蹴れば勝つ可能性は高まる。だけど、そんなことして成長がある? そんな方法論を選択しないのは当たり前。そのうえで勝つために必死に、死に物狂いでやる。そうやって戦った結果、負けてもいい。
小野 そうですね。
岡田 子どもが相手でも、僕は勝つために必死でやれと言う。で、負けても全然問題ない。最初から、こういうサッカーができれば負けてもいいというスタンスだったら、勝っても負けても絶対に進歩はない。俺はそう思っている。
小野 まったく同感です。
岡田 だけど、PTAとかで言うと、ものすごく批判される。「なんであんなに勝て勝て言うのか」と。違うんだよ。負けてもいいけど、勝つために全力を尽くさないといけない。ヨーロッパで子どもの試合を見ると、日本以上に親の声援がすごい。熱い熱い。その代わり、負けても「グッドゲーム」と子どもたちを迎えている。日本のお母さんは違う。「キャー、行け行け」と言ったあと、「なにやってんのよ、アンタ!」と怒り出す。あれはひどいよ。あんまり勝利を求めず、この子の成長だけを願ってとか言うけど、負けた瞬間に怒り出す。あの姿勢は、本当にひどいと思う。
型を破ることで自由な発想が生まれる
小野 子どもたちは、勝ちたい気持ちを絶対に持っているはず。その気持ちを、どうやって大きくしていくのか。その気持ちがあるから、もっとうまくなりたい、もっと練習したいという気持ちが出てくる。
岡田 そうは言っても、俺はもう指導者としては限界だからな。
小野 いやいや、そんなことはありません。とにかく、基本の型があるから自由な発想が出てくるのに、反対になっているところが日本の問題だと思います。先日、ノーベル賞を受賞した本庶佑さんの「教科書に書いてあることをすべて信じてはいけない。教科書が全部正しいなら、科学の進歩はない」という言葉を紹介しながら、iPS細胞の山中伸弥さんが「勘違いしないように。教科書をとことんまで追求して、もっと違うことがあるんじゃないかと探ることが大事だと言いたいんですよ」と補足されていた。あの掛け合いを聞いて、まさにFC今治のことを言っているような気がしました。
岡田 やっぱり、自由なところから自由な発想は生まれないと思う。縛りとか型、抵抗があって、そこを破ろうとする姿勢から自由な発想、自由な人間が生まれてくるんだと思う。“ゆとり世代”を見て、やりたいことを探しなさいという教育方針には限界があると感じる。錦織圭とか松山英樹とか、見つけられた人はすごいことになっている。でも、大半の人は見つけられなくて苦労している。好きなこと、やりたいことを探せと言われても難しい。きっちり授業をしているからこそ、初めて「こんなのつまんねぇ。こっちの方が面白い」という発想が出てくるんじゃないかと思う。
小野 そうですね。何かベースがあるから、それを破る発想が生まれてくる。
※続きは発売中の『サッカーテクニカルレポート 超一流のサッカー分析学』をご覧ください
ーーーーーーーーーーーーー
https://jr-soccer.jp/2019/02/02/post109014/
@ーーーーーーーーーーーーー
【勝敗を度外視して美学にこだわる指導者に、岡田武史と小野剛が覚える違和感】
必死でやって負けても問題ない
岡田 俺は人を批判しない。いろんな人がいていいと思う。みんな同じサッカーだったら面白くない。
小野 みんなが勝ちたいと思って必死にやってきた結果、国民性とかに合ったスタイルが出てくるという考え方は、本当にそうかもしれないですね。最初に戦略があって、それを目指した結果ではなく、勝ちたいと思って努力した結果、スタイルが出てきた。最近、そういうのを「〇〇スクール」という言葉で表現していますね。
岡田 チーム作りと采配の2つがあると、日本人の指導者はチーム作りに美学を感じる人が多い。采配で勝つのは邪道だと。両方大事なんだけど。最後にパワープレーを仕掛けて勝つと、最初からパワープレーやればいいじゃないかという極論が出てくる。いやいや、それはリスクが大き過ぎるだろうと。もちろん、自分のスタイルだけにこだわって、勝敗を度外視してはいけない。絶対に勝つという気持ちを持たないで、スタイルにこだわって、負けてもいいと言い始めると、サッカーは進歩しないと思う。
小野 そこに美学を求めると、確かに進歩がありませんね。
岡田 ポリシーや哲学があるのは当たり前。それで、勝たなきゃいけない。
小野 勝利至上主義に関する賛否の議論も、方法論の話だと思います。その年代以外では通用しない方法論で勝つのはどうかとは思いますけど、とにかく目の前の試合に勝ちたいという気持ちを忘れてはいけない。
岡田 そのとおり。小学生年代ならデカい子を前に置いて、ボーンと蹴れば勝つ可能性は高まる。だけど、そんなことして成長がある? そんな方法論を選択しないのは当たり前。そのうえで勝つために必死に、死に物狂いでやる。そうやって戦った結果、負けてもいい。
小野 そうですね。
岡田 子どもが相手でも、僕は勝つために必死でやれと言う。で、負けても全然問題ない。最初から、こういうサッカーができれば負けてもいいというスタンスだったら、勝っても負けても絶対に進歩はない。俺はそう思っている。
小野 まったく同感です。
岡田 だけど、PTAとかで言うと、ものすごく批判される。「なんであんなに勝て勝て言うのか」と。違うんだよ。負けてもいいけど、勝つために全力を尽くさないといけない。ヨーロッパで子どもの試合を見ると、日本以上に親の声援がすごい。熱い熱い。その代わり、負けても「グッドゲーム」と子どもたちを迎えている。日本のお母さんは違う。「キャー、行け行け」と言ったあと、「なにやってんのよ、アンタ!」と怒り出す。あれはひどいよ。あんまり勝利を求めず、この子の成長だけを願ってとか言うけど、負けた瞬間に怒り出す。あの姿勢は、本当にひどいと思う。
型を破ることで自由な発想が生まれる
小野 子どもたちは、勝ちたい気持ちを絶対に持っているはず。その気持ちを、どうやって大きくしていくのか。その気持ちがあるから、もっとうまくなりたい、もっと練習したいという気持ちが出てくる。
岡田 そうは言っても、俺はもう指導者としては限界だからな。
小野 いやいや、そんなことはありません。とにかく、基本の型があるから自由な発想が出てくるのに、反対になっているところが日本の問題だと思います。先日、ノーベル賞を受賞した本庶佑さんの「教科書に書いてあることをすべて信じてはいけない。教科書が全部正しいなら、科学の進歩はない」という言葉を紹介しながら、iPS細胞の山中伸弥さんが「勘違いしないように。教科書をとことんまで追求して、もっと違うことがあるんじゃないかと探ることが大事だと言いたいんですよ」と補足されていた。あの掛け合いを聞いて、まさにFC今治のことを言っているような気がしました。
岡田 やっぱり、自由なところから自由な発想は生まれないと思う。縛りとか型、抵抗があって、そこを破ろうとする姿勢から自由な発想、自由な人間が生まれてくるんだと思う。“ゆとり世代”を見て、やりたいことを探しなさいという教育方針には限界があると感じる。錦織圭とか松山英樹とか、見つけられた人はすごいことになっている。でも、大半の人は見つけられなくて苦労している。好きなこと、やりたいことを探せと言われても難しい。きっちり授業をしているからこそ、初めて「こんなのつまんねぇ。こっちの方が面白い」という発想が出てくるんじゃないかと思う。
小野 そうですね。何かベースがあるから、それを破る発想が生まれてくる。
※続きは発売中の『サッカーテクニカルレポート 超一流のサッカー分析学』をご覧ください
ーーーーーーーーーーーーー
2018年11月16日
Liga MX (メキシコ1部リーグ)ケレタロFCコーチ
Liga MX (メキシコ1部リーグ)
Gallos Blancos de Querétaro (ガジョス ブランコス デ ケレタロ/ケレタロFC)で、U15~U21分析スタッフ等で活躍している友人の塩沢拓也が来長したので、熱いサッカー談義をしてきました。


たくやはもう6年半もメキシコに住み、自身の夢のため、サッカーの指導力向上のために勉強と実践をプロクラブの環境でし続けています。
メキシコでサッカーライセンスを取得し、今ではメキシコ1部リーグのクラブでスタッフとしてプロ契約結びサッカーを仕事に生きています。
メキシコの育成年代の話しから、たくやが在籍した2チームでの育成哲学の話、仕事として行なっているサッカーの試合分析から育成分析、指導方法などの話を聞き、ノザワナの試合を一緒に観ながら様々な観点からサッカーを解説してくれました。
サッカーの新しい見解や、忘れていた大切なもの、より細かく深く掘り下げる基本の大切さから、その後の発展、応用方法...等々、、
昼過ぎから深夜まで本当に熱心にたくさんの気付きを教えてくれました。
この気付きをクラブの選手達のためにたくさん活かしていきます!!
たくやどうもありがとう!!!
次はノザワナにも顔を出してくれると思うので皆さん楽しみにしていてください。

終わったあと写真撮り忘れていたので明るいスーパーで撮りました(笑)
Gallos Blancos de Querétaro (ガジョス ブランコス デ ケレタロ/ケレタロFC)で、U15~U21分析スタッフ等で活躍している友人の塩沢拓也が来長したので、熱いサッカー談義をしてきました。


たくやはもう6年半もメキシコに住み、自身の夢のため、サッカーの指導力向上のために勉強と実践をプロクラブの環境でし続けています。
メキシコでサッカーライセンスを取得し、今ではメキシコ1部リーグのクラブでスタッフとしてプロ契約結びサッカーを仕事に生きています。
メキシコの育成年代の話しから、たくやが在籍した2チームでの育成哲学の話、仕事として行なっているサッカーの試合分析から育成分析、指導方法などの話を聞き、ノザワナの試合を一緒に観ながら様々な観点からサッカーを解説してくれました。
サッカーの新しい見解や、忘れていた大切なもの、より細かく深く掘り下げる基本の大切さから、その後の発展、応用方法...等々、、
昼過ぎから深夜まで本当に熱心にたくさんの気付きを教えてくれました。
この気付きをクラブの選手達のためにたくさん活かしていきます!!
たくやどうもありがとう!!!
次はノザワナにも顔を出してくれると思うので皆さん楽しみにしていてください。

終わったあと写真撮り忘れていたので明るいスーパーで撮りました(笑)