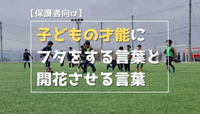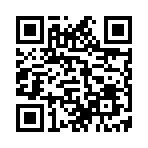2017年04月11日
子育て、教育について、、その2
昨日のバーモントカップ優勝のもう一方では、セカンドチームがチラベルトカップを戦っていました。
結果は残念でしたが、結果以上に、重要なことにビデオを見ていて気付きました。
それは、スペイン遠征→北信越大会→今 に繋がっている課題で、
『自分で判断しているか!?』
『自分で考えて選んでいるか!?』
『自分で責任を持って決断しているか!?』
ということです。
「誰かに言われた判断(プレー)になっていないか?」
「誰かが教えてくれた正解をなぞってるだけじゃないか?」
「誰かが教えてくれるのを待っていないか?」
と、見えるプレーがまだまだありました。
それとは反対に、僕のいないところでも関係なしに、
自信を持って!
強気にプレーする!
頼もしい選手もいました!!!
よくよく分析すると、、
①頭で解っていて、体も勝手に動く選手
(体でも覚えていて、能動的に体を動かせる)
②頭で解っていて、頭で考えてから体を動かせる選手
(頭で考えてから動かすために、スピードは少し遅くなる)
③頭では解っていなくても、体が勝手に動く選手
(センスの良い選手。将来的には頭でも解って動かせることが重要)
④頭で解っているけど、試合の中で実際にプレーすると解らなくなる
(良い練習と良い指導が必要)
⑤頭で解っているふりになってしまっていて、コーチの言葉を真似している選手
(本質的には理解せずに、コーチの「言葉」だけ覚えてる)
(この場合、試合中には筋肉だけ動かしてプレーするか、周りからの指示によってプレーすることになる)
今回は僕のいないところで選手達がどんなプレーをするのか、
ビデオで観れたことがとても大きな収穫でした。
上記の⑤の選手について、最近の僕の考えを記したいと思います。
『自分に対して自信持っている』=ヤンチャタイプ
『言われたことを守ることに自信を持っている』=優等生タイプ(とします。)
⑤の選手に多いのは、優等生タイプが多い印象です。
「言われたことは徹底的にできる!!」
だけど、、
「言われていないこと」に対して頭がフリーズしてしまう。
現時点で、
『自分に自信がない』
ということだと思います。
根本原因は、
『言われたことをやることが、「正解」だと思っている』
誰かの「正解」に習うことが、「正解」だと思っているのが優等生タイプ??(表現は難しいですが、)
なのではないかと考えます。
そもそも、
「正解」なんてものは1つではない!!!
と考えます。
『ゴール』
は1つでも、方法はたくさんあります。
上手くいけば「正解」だし、
上手くいかなければ「失敗??」
だとしても、
それは「学び」「成長」に繋げます!!!
話しを戻しますが、
⑤の選手は、優等生タイプで、
「誰かの正解に生きている」気がします。
自分の、
『オリジナル』で、
『自分の考えで』
『自分のやり方で』
『他人とコミュニケーションをとりながら』
『試しにやってみる!!』
そして、失敗しても、
『自分で責任を取る方法を知っている』
『失敗から学び、成長する方法を知っている』
そんな人間が、サッカーの中では、成長し、活躍していくと確信しています!!!
先ずは、
『根本』『ゴール』『目的』
をしっかり押さえている。
それに向かう方法は、誰かの正解ではなくて、、
『自分の考えで』
『自分のやり方で』
『他人とコミュニケーションをとりながら』
『試しにやってみる!!』
という、独創性に富んだ、他の人では思い付かないことができるような、
魅力的な選手に、人間になっていってほしいと思います。
ノザワナの選手達は、
誰かに言われたことを、言われた通りにそのままやる、、
なんて、そんな選手にはなってほしくないと思います。
そのためには、サッカー現場では、
『根本』『ゴール』『目的』
をしっかり丁寧に理解できるまでティーチングし、
それに向かうための方法は、
『教えないで導く、気付かせる、コーチング』
を徹底してクオリティを上げていきます。
ご家庭では、、
誰かの正解に生きる優等生タイプ、ではなく、、
『自分の「考え」「判断」「行動」「コミュニケーション」』
に、
『責任』と『自信』
を持てるように、
いっぱい本人の考え方を尊重して、本人の考えと判断の下、
「失敗と成功の経験」
を、たくさんさせてあげて、
※※※親が失敗しないように『正解に導く』のではなく、
たくさん失敗させてあげて、
そこからの、
『責任の取り方』
『失敗からの学び方』
『失敗からの成長の仕方』
を、導いてあげて
「誰かの正解」ではなく、
『自分自身の考え、判断、行動、責任、コミュニケーション』に、
自信を持てるようにしてあげてほしいと思います。
そすれば、サッカーの試合の中で、
主体的に、
能動的に、
こちらの考えを凌駕するような、
魅力的なプレーにたくさんチャレンジできるようになるのではないかと思います。
今回バーモントカップ優勝しましたが、僕はチーム全員の成長を望んでいます。
チーム全員が成長し、全員が魅力的な選手であり、人間になることを強く望んでいます。
これからの全員の成長を全力でサポートしていきます!!!!
結果は残念でしたが、結果以上に、重要なことにビデオを見ていて気付きました。
それは、スペイン遠征→北信越大会→今 に繋がっている課題で、
『自分で判断しているか!?』
『自分で考えて選んでいるか!?』
『自分で責任を持って決断しているか!?』
ということです。
「誰かに言われた判断(プレー)になっていないか?」
「誰かが教えてくれた正解をなぞってるだけじゃないか?」
「誰かが教えてくれるのを待っていないか?」
と、見えるプレーがまだまだありました。
それとは反対に、僕のいないところでも関係なしに、
自信を持って!
強気にプレーする!
頼もしい選手もいました!!!
よくよく分析すると、、
①頭で解っていて、体も勝手に動く選手
(体でも覚えていて、能動的に体を動かせる)
②頭で解っていて、頭で考えてから体を動かせる選手
(頭で考えてから動かすために、スピードは少し遅くなる)
③頭では解っていなくても、体が勝手に動く選手
(センスの良い選手。将来的には頭でも解って動かせることが重要)
④頭で解っているけど、試合の中で実際にプレーすると解らなくなる
(良い練習と良い指導が必要)
⑤頭で解っているふりになってしまっていて、コーチの言葉を真似している選手
(本質的には理解せずに、コーチの「言葉」だけ覚えてる)
(この場合、試合中には筋肉だけ動かしてプレーするか、周りからの指示によってプレーすることになる)
今回は僕のいないところで選手達がどんなプレーをするのか、
ビデオで観れたことがとても大きな収穫でした。
上記の⑤の選手について、最近の僕の考えを記したいと思います。
『自分に対して自信持っている』=ヤンチャタイプ
『言われたことを守ることに自信を持っている』=優等生タイプ(とします。)
⑤の選手に多いのは、優等生タイプが多い印象です。
「言われたことは徹底的にできる!!」
だけど、、
「言われていないこと」に対して頭がフリーズしてしまう。
現時点で、
『自分に自信がない』
ということだと思います。
根本原因は、
『言われたことをやることが、「正解」だと思っている』
誰かの「正解」に習うことが、「正解」だと思っているのが優等生タイプ??(表現は難しいですが、)
なのではないかと考えます。
そもそも、
「正解」なんてものは1つではない!!!
と考えます。
『ゴール』
は1つでも、方法はたくさんあります。
上手くいけば「正解」だし、
上手くいかなければ「失敗??」
だとしても、
それは「学び」「成長」に繋げます!!!
話しを戻しますが、
⑤の選手は、優等生タイプで、
「誰かの正解に生きている」気がします。
自分の、
『オリジナル』で、
『自分の考えで』
『自分のやり方で』
『他人とコミュニケーションをとりながら』
『試しにやってみる!!』
そして、失敗しても、
『自分で責任を取る方法を知っている』
『失敗から学び、成長する方法を知っている』
そんな人間が、サッカーの中では、成長し、活躍していくと確信しています!!!
先ずは、
『根本』『ゴール』『目的』
をしっかり押さえている。
それに向かう方法は、誰かの正解ではなくて、、
『自分の考えで』
『自分のやり方で』
『他人とコミュニケーションをとりながら』
『試しにやってみる!!』
という、独創性に富んだ、他の人では思い付かないことができるような、
魅力的な選手に、人間になっていってほしいと思います。
ノザワナの選手達は、
誰かに言われたことを、言われた通りにそのままやる、、
なんて、そんな選手にはなってほしくないと思います。
そのためには、サッカー現場では、
『根本』『ゴール』『目的』
をしっかり丁寧に理解できるまでティーチングし、
それに向かうための方法は、
『教えないで導く、気付かせる、コーチング』
を徹底してクオリティを上げていきます。
ご家庭では、、
誰かの正解に生きる優等生タイプ、ではなく、、
『自分の「考え」「判断」「行動」「コミュニケーション」』
に、
『責任』と『自信』
を持てるように、
いっぱい本人の考え方を尊重して、本人の考えと判断の下、
「失敗と成功の経験」
を、たくさんさせてあげて、
※※※親が失敗しないように『正解に導く』のではなく、
たくさん失敗させてあげて、
そこからの、
『責任の取り方』
『失敗からの学び方』
『失敗からの成長の仕方』
を、導いてあげて
「誰かの正解」ではなく、
『自分自身の考え、判断、行動、責任、コミュニケーション』に、
自信を持てるようにしてあげてほしいと思います。
そすれば、サッカーの試合の中で、
主体的に、
能動的に、
こちらの考えを凌駕するような、
魅力的なプレーにたくさんチャレンジできるようになるのではないかと思います。
今回バーモントカップ優勝しましたが、僕はチーム全員の成長を望んでいます。
チーム全員が成長し、全員が魅力的な選手であり、人間になることを強く望んでいます。
これからの全員の成長を全力でサポートしていきます!!!!
新しいBlogをよろしくお願いします。
『夢を実現させる”脳”の使い方』活動報告
【“自信の力”よりも大きな”他信の力”】
チームスタートミーティング
全柔連が小学生の全国大会を廃止
2.25日経新聞:カズ『挑戦するだけで成功』
『夢を実現させる”脳”の使い方』活動報告
【“自信の力”よりも大きな”他信の力”】
チームスタートミーティング
全柔連が小学生の全国大会を廃止
2.25日経新聞:カズ『挑戦するだけで成功』
この記事へのコメント
責任って言葉が多いですね。
その言葉が挑戦の邪魔をし、失敗が許されない環境を作っていきます。
今は失敗、挑戦をとにかく繰り返して考えていく時期と感じます。
取り返し方を覚えてきたところでそこで初めて、それが責任と知るんじゃないでしょうか。
子供達にとって失敗からの責任の取り方も挑戦です。
責任という言葉は子供達に想像以上に重くのしかかります。
優等生タイプは特に重く受け止めるので消極的になっていくように感じています。
これは大人も同じじゃないでしょうか?
子育てもテーマとなっていますが、挑戦させるのも親の役目。
それに対しての責任を取るのも親の役目です。
責任を意識させる前に、指導者にも挑戦を邪魔しない環境を作る責任があると感じています。
突然、失礼な事を書いてしまい申し訳ありません。
その言葉が挑戦の邪魔をし、失敗が許されない環境を作っていきます。
今は失敗、挑戦をとにかく繰り返して考えていく時期と感じます。
取り返し方を覚えてきたところでそこで初めて、それが責任と知るんじゃないでしょうか。
子供達にとって失敗からの責任の取り方も挑戦です。
責任という言葉は子供達に想像以上に重くのしかかります。
優等生タイプは特に重く受け止めるので消極的になっていくように感じています。
これは大人も同じじゃないでしょうか?
子育てもテーマとなっていますが、挑戦させるのも親の役目。
それに対しての責任を取るのも親の役目です。
責任を意識させる前に、指導者にも挑戦を邪魔しない環境を作る責任があると感じています。
突然、失礼な事を書いてしまい申し訳ありません。
Posted by hajime at 2017年04月12日 12:27
ハジメ様
ご意見ありがとうございます。
その様な考え方もありますね、なるほどです!
僕が考えるのは、「責任」という言葉に対してプレッシャーが掛かるのは、どうやって責任を取ったら良いのか分からないからだと考えています。僕自身もそうですが。
失敗してもどの様に対処すれば良いか、乗り越えれば良いか、解決すれば良いか、失敗しても乗り越える方法、解決する方法を知っていて、自分で考えて仲間と共に解決することができることで、失敗や責任という言葉は怖くなくると考えています。
だから、上記の問題解決能力が備わることで、たくさんチャレンジできると思います。
もちろん、仰る通り、指導者がチャレンジの邪魔をしないことや、失敗した時にどんな関わり方をするのかがとても重要なことは大前提です。
勝山
ご意見ありがとうございます。
その様な考え方もありますね、なるほどです!
僕が考えるのは、「責任」という言葉に対してプレッシャーが掛かるのは、どうやって責任を取ったら良いのか分からないからだと考えています。僕自身もそうですが。
失敗してもどの様に対処すれば良いか、乗り越えれば良いか、解決すれば良いか、失敗しても乗り越える方法、解決する方法を知っていて、自分で考えて仲間と共に解決することができることで、失敗や責任という言葉は怖くなくると考えています。
だから、上記の問題解決能力が備わることで、たくさんチャレンジできると思います。
もちろん、仰る通り、指導者がチャレンジの邪魔をしないことや、失敗した時にどんな関わり方をするのかがとても重要なことは大前提です。
勝山
Posted by ノザワナFC at 2017年04月12日 12:52
at 2017年04月12日 12:52
 at 2017年04月12日 12:52
at 2017年04月12日 12:52