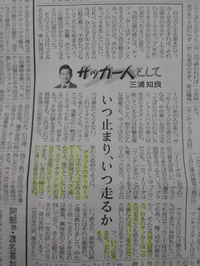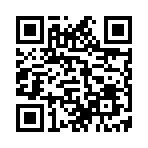2023年01月30日
2021年05月10日
2020年11月06日
【ノザワナ FC スタッフ募集】
【ノザワナ FC スタッフ募集】

一緒に子ども達の”成長”と”夢”をサポートする仲間を募集します。
子どもに対する愛情と情熱があり主体的な方。
サッカー経験やサッカー指導歴以上に、愛情・情熱・主体性のある方と一緒に良い環境を創っていきたいと思います。
興味のある方は詳細をご案内しますので下記までお問合せください❗️
お気軽にご連絡ください!
お待ちしてます♪
【NOZAWANA FC】
mail:nozawana.fc@gmail.com
tell:026-405-5145

一緒に子ども達の”成長”と”夢”をサポートする仲間を募集します。
子どもに対する愛情と情熱があり主体的な方。
サッカー経験やサッカー指導歴以上に、愛情・情熱・主体性のある方と一緒に良い環境を創っていきたいと思います。
興味のある方は詳細をご案内しますので下記までお問合せください❗️
お気軽にご連絡ください!
お待ちしてます♪
【NOZAWANA FC】
mail:nozawana.fc@gmail.com
tell:026-405-5145
2019年02月05日
「メモを取る習慣が弱者を強くする」 長く結果を出し続けるには勘では足りない
東洋経済onlineから、、
【野村克也「メモを取る習慣が弱者を強くする」
長く結果を出し続けるには勘では足りない】
https://toyokeizai.net/articles/-/259653?display=b
@ーーーーーーーーーーーーー
野球界で現役、監督時代を通じ輝かしい戦歴を誇る野村克也氏は、周囲から「メモ魔」と呼ばれていたそうです。試行錯誤した新人時代や弱小球団を率いたときも、毎日欠かすことのなかったメモによって自らを高め、チームをまとめ、強者に勝利してきました。メモをどのように役立てたのか、野村氏が語ります。
メモによって一軍定着
かつて私が著した『野村ノート』(小学館)は、50年にわたる野球界での生活の中で蓄積してきた私なりの考えを1冊にまとめたものだ。実はこの本のベースとなったのが、現役時代から私が毎日のようにつけてきたいくつもの「メモ」である。
京都の峰山高校から契約金なしのテスト生として南海ホークスに入団したのが1954(昭和29)年のこと。プロ1年目は代打などで9試合に出場したものの11打席ノーヒットに終わり、2年目も一軍に上がれないままファーム暮らしで終わってしまった。
「来年こそクビになるのでは?」そんな不安をつねに抱えていたが、努力だけは怠らなかった。試行錯誤を続けながらほかの選手の3倍、いや4倍は努力していたと思う。その結果、私はプロ3年目にしてようやく一軍に定着することができた。
私がメモを取るようになったのはちょうどこの頃のことだ。
メモを取るようになったのは誰かの助言などがあったからではなく、あくまでも自主的に始めたものだった。私は頭が悪いうえに、人一倍不器用である。そんな私が相手チームの打者や投手の情報を頭に入れ、攻略の糸口を見つけていくにはメモを取るしか方法がなかった。そんなわけで、生きていくうえで必要だったから、私は自然とメモを取るようになったのである。
ロッカールームなどで私が始終メモをつけているものだから、周囲の人たちは私を「メモ魔」と呼んだ。メモしていたのは、主に相手打者の特徴(長所・短所)である。試合のあった日はロッカールームや帰りの移動バスの中で、その日対戦した打者の対戦結果をひもときながら、その打者の長所(好きな球種、コースなど)や短所(苦手な球種、コースなど)を記していった。なぜヒットを打たれたのか、あるいは抑えることができたのかを考え、それらを克明にメモし、家に帰ってからそれらをノートにまとめた。
人間とは不思議なもので、1晩経つと前の日にあった細かいことのほとんどは忘れてしまっている。私の場合、1試合マスクを被れば、どんなに少なくても約30回は相手打者と対戦するわけで、その1打席1打席、1球1球を毎日脳に記憶し続けることなど到底不可能である。だから私は、その日あったことはその日のうちに必ずメモするようにしていた。夜中、メモを書き記しているうちにゲーム中の興奮がよみがえって眠れなくなってしまい、気がつけば夜が白々と明けていたなどということもしょっちゅうだった。
毎日毎日、ちょっとずつメモを取っていく。これは実に地道な作業であり、根気を要することだ。でも、こういった小さな積み重ねがあったからこそ、私は後に選手として3017試合に出場することができ(日本プロ野球史上2位)、さらに監督として通算1565勝(同5位)という成績を収めることができた。
メモは学びの宝庫だ
3年目に一軍に定着してからというもの、私はシーズン中はメモを取り続け、就寝前にノートにまとめ、その積み重ねによって正捕手の座を獲得することができた。しばらく経ってから以前書いたメモを読み返してみると、「あ、こんなことがあったのか」とか「この時の自分はこんなことを考えていたのか」などと改めて気づくこと、反省することが出てきたりするから、そういった意味でもメモは「学びの宝庫」であるといえるだろう。
思えば学生時代、授業中に取っていたノートこそ、学びの原点である。私はそれほど優秀な生徒ではなかったので、ノートをこまめに取るようなタイプでは決してなかった。でも、大人になり、プロの世界に入ってから始めた「メモを取る」という作業はさほど苦ではなかったし、メモを取れば取るほどその大切さを思い知った。
メモが学びの宝庫であることは、キリスト教の『新約聖書』や儒家の祖である孔子の残した『論語』といった、先人たちが残してきた偉大な書物を見ても明らかである。『新約聖書』は、イエス・キリストが布教活動の中で発した言葉を弟子たちが一冊の本にまとめたものであるし、『論語』も孔子がその弟子たちと交わした問答が記録されている。『新約聖書』は2000年、『論語』は2500年の歳月を経てもなお、人々の間で読み継がれているのだから、私はその事実を目の前にして、メモの大切さを改めて思い知るとともに、メモが学びとなり、人を育てるのだと確信している。
現役時代、ほぼ毎日メモを取り続けていた私だが、ではいったいどのようなメモを取っていたのか、ここで具体的にご紹介したいと思う。
先述したように私がメモしていたのは主に相手打者の長所、短所、そして投手のクセといったものである。とくに「投手のクセ」は短期間で変わる(その投手がクセを見破られていることを察し、フォームを変える)ことが多く、メモを見直してはその都度、変更点を書き込むようにしていた。
ある投手のクセとして当時の私はこんなことを書いている。
ワインドアップで帽子のマークが見えないとストレート、見えるとカーブ。
ワインドアップとは、投手が投球動作に入る前に両腕を頭の上に掲げるフォームのことで、この時、ボールの握り方によって両腕の開き具合にちょっとした差が出る。私はそういった投手のクセに気づくたび、メモを取るようにしていた。ちなみにその投手に関しては後日、メモに赤字で「ワインドアップでのクセは修正されている」と記している。このように私は投手のクセの変化を見逃さないよう、つねに細心の注意を払って観察し、新しい情報を得るとすぐに書き直していた。
投手のクセはフォーム以外にも、捕手の出したサインにうなずくときの「うなずき方」などにも表れた。元読売巨人軍の西本聖投手は切れ味鋭いシュートで打者を打ち取る好投手だったが、その球種に人一倍自信があるものだから捕手がシュートのサインを出すといつも以上に深くうなずくことが多かった。
プロセスを大事にする人はメモを残す
投手によっては自分が不得意な球種、あるいはその日の調子がイマイチな球種を要求された際に「自信のなさそうなうなずき方(あいまいなうなずき方)」をする投手もいた。私は肉体的な変化に加え、そういった「投手の性格」も把握しながらクセを見抜くようにし、それを毎日メモしていた。
手前みそだが、私は投手のこうしたさまざまなクセを見破るすべに長けていたのだと思う。だからこそ、戦後初の三冠王や通算本塁打657本、通算安打数2901本(ともに歴代2位)という好成績を収めることができたのだろう。
ヤクルトスワローズで監督をしていた時の正捕手の古田敦也、さらに楽天イーグルス時代の正捕手・嶋基宏、この2人に私はいつもベンチで語りかけていた。守備から帰ってきた彼らに対し、「あの時投げさせた球種、コースの根拠は何や?」と。
捕手が配球を考えるとき、選択肢は大きく分けると次の形になる。
・インコースか? アウトコース?
・高めか? 低めか?
・ストレートか? 変化球か?
・ストライクか? ボールか?
捕手が「投手に何を投げさせるか?」を考えるのは、これらを組み合わせた16種である。ゲームはいま何イニング目か? 点差は? ボールカウントは? アウトカウントは? さらにその打者は前の打席でどのような対応をしたか? あるいは前の投球にどのように対応したか? ベンチからのサインは? 捕手はそういったことをすべて考慮したうえで、投手に「次はこのボール」とサインを出すわけで、そこには確かな根拠がなければならない。
だから私が古田や嶋にその根拠を問うたとき、彼らが「直感で……」とか「何となく……」というような返答をしてきたときには「何を言っとるんだ!」と叱りつけることもたびたびあった。
結果よりもプロセスが大事
私は現役時代から捕手としてつねに「結果よりもプロセスが大事」と思ってやってきた。適当に出したサインで相手打者を抑えたとしても、次に生かすことのできない根拠なき配球では何の意味も持たない。根拠のある配球なら、たとえ打たれたとしてもその失敗を次に生かすことができる。
これは野球に限らず、いろいろな仕事においても同じことが言えるのではないだろうか。「結果を出せば何をしてもいい」とばかりに仕事をしていても、そのような適当なやり方では長く結果を残し続けることは決してできない。
プロセスを大切にしたいなら、常日頃から「〇〇とは?」と問題意識を持って考え、自分なりの答えをメモし続けることが重要である。
毎日、何でもいい。「この仕事の意味は?」「利益を上げるには?」「どうやったら相手に喜んでもらえるか?」そういったことを問い続け、自分なりの答えをメモしてみたらどうだろう。同じ質問でも、時が経てば答えが変わることもある。その変化を「自分の成長」として確認できるのも、メモの大きな利点といえよう。
長く結果を出し続けている人、あるいは社会から評価される成功者たちは皆つねに「〇〇とは?」と根拠を問い続けている。皆さんにもぜひ、そんな「プロセスを大切にする生き方」をしてほしい。
ーーーーーーーーーーーーー
【野村克也「メモを取る習慣が弱者を強くする」
長く結果を出し続けるには勘では足りない】
https://toyokeizai.net/articles/-/259653?display=b
@ーーーーーーーーーーーーー
野球界で現役、監督時代を通じ輝かしい戦歴を誇る野村克也氏は、周囲から「メモ魔」と呼ばれていたそうです。試行錯誤した新人時代や弱小球団を率いたときも、毎日欠かすことのなかったメモによって自らを高め、チームをまとめ、強者に勝利してきました。メモをどのように役立てたのか、野村氏が語ります。
メモによって一軍定着
かつて私が著した『野村ノート』(小学館)は、50年にわたる野球界での生活の中で蓄積してきた私なりの考えを1冊にまとめたものだ。実はこの本のベースとなったのが、現役時代から私が毎日のようにつけてきたいくつもの「メモ」である。
京都の峰山高校から契約金なしのテスト生として南海ホークスに入団したのが1954(昭和29)年のこと。プロ1年目は代打などで9試合に出場したものの11打席ノーヒットに終わり、2年目も一軍に上がれないままファーム暮らしで終わってしまった。
「来年こそクビになるのでは?」そんな不安をつねに抱えていたが、努力だけは怠らなかった。試行錯誤を続けながらほかの選手の3倍、いや4倍は努力していたと思う。その結果、私はプロ3年目にしてようやく一軍に定着することができた。
私がメモを取るようになったのはちょうどこの頃のことだ。
メモを取るようになったのは誰かの助言などがあったからではなく、あくまでも自主的に始めたものだった。私は頭が悪いうえに、人一倍不器用である。そんな私が相手チームの打者や投手の情報を頭に入れ、攻略の糸口を見つけていくにはメモを取るしか方法がなかった。そんなわけで、生きていくうえで必要だったから、私は自然とメモを取るようになったのである。
ロッカールームなどで私が始終メモをつけているものだから、周囲の人たちは私を「メモ魔」と呼んだ。メモしていたのは、主に相手打者の特徴(長所・短所)である。試合のあった日はロッカールームや帰りの移動バスの中で、その日対戦した打者の対戦結果をひもときながら、その打者の長所(好きな球種、コースなど)や短所(苦手な球種、コースなど)を記していった。なぜヒットを打たれたのか、あるいは抑えることができたのかを考え、それらを克明にメモし、家に帰ってからそれらをノートにまとめた。
人間とは不思議なもので、1晩経つと前の日にあった細かいことのほとんどは忘れてしまっている。私の場合、1試合マスクを被れば、どんなに少なくても約30回は相手打者と対戦するわけで、その1打席1打席、1球1球を毎日脳に記憶し続けることなど到底不可能である。だから私は、その日あったことはその日のうちに必ずメモするようにしていた。夜中、メモを書き記しているうちにゲーム中の興奮がよみがえって眠れなくなってしまい、気がつけば夜が白々と明けていたなどということもしょっちゅうだった。
毎日毎日、ちょっとずつメモを取っていく。これは実に地道な作業であり、根気を要することだ。でも、こういった小さな積み重ねがあったからこそ、私は後に選手として3017試合に出場することができ(日本プロ野球史上2位)、さらに監督として通算1565勝(同5位)という成績を収めることができた。
メモは学びの宝庫だ
3年目に一軍に定着してからというもの、私はシーズン中はメモを取り続け、就寝前にノートにまとめ、その積み重ねによって正捕手の座を獲得することができた。しばらく経ってから以前書いたメモを読み返してみると、「あ、こんなことがあったのか」とか「この時の自分はこんなことを考えていたのか」などと改めて気づくこと、反省することが出てきたりするから、そういった意味でもメモは「学びの宝庫」であるといえるだろう。
思えば学生時代、授業中に取っていたノートこそ、学びの原点である。私はそれほど優秀な生徒ではなかったので、ノートをこまめに取るようなタイプでは決してなかった。でも、大人になり、プロの世界に入ってから始めた「メモを取る」という作業はさほど苦ではなかったし、メモを取れば取るほどその大切さを思い知った。
メモが学びの宝庫であることは、キリスト教の『新約聖書』や儒家の祖である孔子の残した『論語』といった、先人たちが残してきた偉大な書物を見ても明らかである。『新約聖書』は、イエス・キリストが布教活動の中で発した言葉を弟子たちが一冊の本にまとめたものであるし、『論語』も孔子がその弟子たちと交わした問答が記録されている。『新約聖書』は2000年、『論語』は2500年の歳月を経てもなお、人々の間で読み継がれているのだから、私はその事実を目の前にして、メモの大切さを改めて思い知るとともに、メモが学びとなり、人を育てるのだと確信している。
現役時代、ほぼ毎日メモを取り続けていた私だが、ではいったいどのようなメモを取っていたのか、ここで具体的にご紹介したいと思う。
先述したように私がメモしていたのは主に相手打者の長所、短所、そして投手のクセといったものである。とくに「投手のクセ」は短期間で変わる(その投手がクセを見破られていることを察し、フォームを変える)ことが多く、メモを見直してはその都度、変更点を書き込むようにしていた。
ある投手のクセとして当時の私はこんなことを書いている。
ワインドアップで帽子のマークが見えないとストレート、見えるとカーブ。
ワインドアップとは、投手が投球動作に入る前に両腕を頭の上に掲げるフォームのことで、この時、ボールの握り方によって両腕の開き具合にちょっとした差が出る。私はそういった投手のクセに気づくたび、メモを取るようにしていた。ちなみにその投手に関しては後日、メモに赤字で「ワインドアップでのクセは修正されている」と記している。このように私は投手のクセの変化を見逃さないよう、つねに細心の注意を払って観察し、新しい情報を得るとすぐに書き直していた。
投手のクセはフォーム以外にも、捕手の出したサインにうなずくときの「うなずき方」などにも表れた。元読売巨人軍の西本聖投手は切れ味鋭いシュートで打者を打ち取る好投手だったが、その球種に人一倍自信があるものだから捕手がシュートのサインを出すといつも以上に深くうなずくことが多かった。
プロセスを大事にする人はメモを残す
投手によっては自分が不得意な球種、あるいはその日の調子がイマイチな球種を要求された際に「自信のなさそうなうなずき方(あいまいなうなずき方)」をする投手もいた。私は肉体的な変化に加え、そういった「投手の性格」も把握しながらクセを見抜くようにし、それを毎日メモしていた。
手前みそだが、私は投手のこうしたさまざまなクセを見破るすべに長けていたのだと思う。だからこそ、戦後初の三冠王や通算本塁打657本、通算安打数2901本(ともに歴代2位)という好成績を収めることができたのだろう。
ヤクルトスワローズで監督をしていた時の正捕手の古田敦也、さらに楽天イーグルス時代の正捕手・嶋基宏、この2人に私はいつもベンチで語りかけていた。守備から帰ってきた彼らに対し、「あの時投げさせた球種、コースの根拠は何や?」と。
捕手が配球を考えるとき、選択肢は大きく分けると次の形になる。
・インコースか? アウトコース?
・高めか? 低めか?
・ストレートか? 変化球か?
・ストライクか? ボールか?
捕手が「投手に何を投げさせるか?」を考えるのは、これらを組み合わせた16種である。ゲームはいま何イニング目か? 点差は? ボールカウントは? アウトカウントは? さらにその打者は前の打席でどのような対応をしたか? あるいは前の投球にどのように対応したか? ベンチからのサインは? 捕手はそういったことをすべて考慮したうえで、投手に「次はこのボール」とサインを出すわけで、そこには確かな根拠がなければならない。
だから私が古田や嶋にその根拠を問うたとき、彼らが「直感で……」とか「何となく……」というような返答をしてきたときには「何を言っとるんだ!」と叱りつけることもたびたびあった。
結果よりもプロセスが大事
私は現役時代から捕手としてつねに「結果よりもプロセスが大事」と思ってやってきた。適当に出したサインで相手打者を抑えたとしても、次に生かすことのできない根拠なき配球では何の意味も持たない。根拠のある配球なら、たとえ打たれたとしてもその失敗を次に生かすことができる。
これは野球に限らず、いろいろな仕事においても同じことが言えるのではないだろうか。「結果を出せば何をしてもいい」とばかりに仕事をしていても、そのような適当なやり方では長く結果を残し続けることは決してできない。
プロセスを大切にしたいなら、常日頃から「〇〇とは?」と問題意識を持って考え、自分なりの答えをメモし続けることが重要である。
毎日、何でもいい。「この仕事の意味は?」「利益を上げるには?」「どうやったら相手に喜んでもらえるか?」そういったことを問い続け、自分なりの答えをメモしてみたらどうだろう。同じ質問でも、時が経てば答えが変わることもある。その変化を「自分の成長」として確認できるのも、メモの大きな利点といえよう。
長く結果を出し続けている人、あるいは社会から評価される成功者たちは皆つねに「〇〇とは?」と根拠を問い続けている。皆さんにもぜひ、そんな「プロセスを大切にする生き方」をしてほしい。
ーーーーーーーーーーーーー
2019年02月05日
プロになる子の親の「共通点」
こちらも、『サカイク』のコラムから、
指導者も保護者にも勉強になる記事です。
読んでみてください!
https://www.sakaiku.jp/column/thought/2019/013901.html
@ーーーーーーーーーーーーー
【親の言動が子どものチャンスを潰している! Jリーガーを続々生み出すサッカー部監督が語る、プロになる子の親の「共通点」】
全国大会の出場経験がないにも関わらず、毎年のようにJリーガーが誕生する興国高校(大阪)。監督を務める内野智章さんに「子どもをプロ選手にするために、保護者がすべきこと」について聞きました。
全国大会出場経験がないにも関わらず毎年のようにJリーガーが誕生する興国高校サッカー部
■保護者は子どものカーナビにならない
興國サッカー部は入部時に、1年生と保護者を集めて「入部前説明会」を行います。この場では部の説明やサッカースタイルなどの話をするのですが、僕が保護者の方に言うのが「息子さんのカーナビになっていませんか?」ということです。
カーナビ通りに行けば、目的地に簡単に着くでしょう。でもそれが、息子さんにとって本当にベストな道なのでしょうか? 道を間違えることによって、より良い道を覚えるのではないでしょうか?
道を間違って、行き止まりになったときに「こっちちゃうわ。あっちの道に行こう」というのも経験です。保護者は子どもより経験があるぶん、「こっちに行ったほうがいい」とアドバイスができますが、その指示通りに動いていても、経験値が溜まらないですよね。カーナビに頼っていたら、道をまったく覚えないのと同じです。しまいには、カーナビがないとどこにも行けなくなる。そんな子どもにしたいのでしょうか?
渋滞にはまったり、事故で道がふさがったときに、カーナビに頼っていては前に進めません。ナビには無い抜け道を瞬時に思いつき、「この道で行けば大丈夫」と思えるかどうか。
そのためには普段から自分で考えて行動して、経験を積み重ねていくしかないんです。
保護者がすべきは、東京に行きたいのに、九州の方を向いて走っていたら「おい、そっちちゃうで」と教えてあげるぐらいでいいんです。大阪から東京に行くのに、中央道で行こうが、新東名で行こうが、どちらでもいい。そこは子どもに任せましょう。でも、山陽道を走っていたら「そっちちゃうで」と。
極端な話、大阪から新潟経由で日本海を回っても、東京に着きますからね。めっちゃ時間かかりますけど(笑)。軌道修正するべきは、子どもが目標から真反対を向いている時。それ以外は口出しせず、基本的には放っておくぐらいでいいのではないでしょうか。
■子どもの不満を聞いてあげる
息子さんの試合を見に来るのは大歓迎。保護者にも「見に来てあげてください」と言っていますが「サッカーのことに関しては、あまり言わないであげてください」と念を押しています。
それよりも、息子さんが、僕ら指導スタッフに不満があるのであれば、文句を聞いてあげてください。そこで、「そうなんや、大変やな、頑張りや」と言ってあげるだけで、ガス抜きになりますから。
そこで一番やってはいけないのが、子どもと一緒に指導スタッフの文句を言うこと。そうなると、軌道修正ができないので伸びません。「監督にそんなこと言われたんか。大変やな」と聞いてあげて、どうしても我慢できなければ、子どもの知らないところで、僕に直接意見を言いに来て下さい。
ただ、誤解してほしくないのは、あなたの子どものために興國サッカー部があるのではないということです。チームの理想を追求するために選手がいて、僕はその理想を追求するために、チームのプレーモデルをより高いレベルで実行できる選手を選ぶわけです。そこで、「いや、私の理想はこうだから」と選手や保護者から言われても、僕にはどうすることもできません。
保護者は子どものサポーターでいてあげてほしいと思います。負けている時はめっちゃ応援して、勝ったらめっちゃ喜ぶ。いいサポーターになってください。評論家はいりません。保護者が評論家になって「監督のサッカーはこうだから」と言い出すと、子どもも頭でっかちになって、現実から目をそむけてしまうんです。
自分の技術や努力が足りていないのに、監督のせいにしてふてくされてもいいことないですよね。社会に出たときに、上司は選べません。でも、自分で入りたくてその会社の面接を受けたわけですよね。それならば、どうすれば上司に認められるか、自分に求められているものはなにかを考えながら、努力をしていくしかないんです。
■プロに進む選手の保護者に共通すること
興國からプロに行った選手の家庭に共通しているのは、保護者が明るくて、試合をよく見に来てくれていたことです。すごく応援し、サッカーのことについては一切口出しをしませんでした。僕とも友好的にコミュニケーションをとりますし、こちらからしない限り、サッカーの話はしません。「監督、元気? いろいろ大変やね」みたいな感じで、世間話をしてケラケラ笑っています。
たまに僕が「ちょっと、おたくの息子さん、僕のことなめてますよ。この前、こんなこと言われたんですけど(笑)」とかフランクに話して「あら、すんません。私からも言っておきますんで」みたいな。これも大阪のノリですよね。
ただ、子どもが入学する前には、すごく熱心に質問をする方もいます。進路のことやケガをしたときにどうするのかなど、親の立場として心配なこともありますからね。でも、入学した後には一切言ってきません。プロに行く選手、大学で活躍する選手の保護者は、 99 %そのタイプです。
なかには自分も若い頃はサッカーをしていて、詳しいお父さんもいます。僕に対して、言いたいこともあるのではと思いますが、ほとんど何も言ってきません。「いつもありがとうございます」みたいな感じで、僕も「こちらこそ、ありがとうございます」というようなスタンスですね。
だから、僕としても選手に気を使わずに指導ができるんです。「こんなことを言ったら、親からクレームが来るかな?」と少しでも頭をよぎったら、言葉を選んでしまいますよね。そうすると指導するタイミングを逃すし、こっちの本気も伝わりきらないんです。
ガツンとぶつかることができると、遠慮なく言えるし、深く関わることができます。だから、選手も本気になってくれるんだと思います。
■親の言動で子どものチャンスが潰れる
才能がある選手の中に、親の関わりによってダメになる子はたくさんいます。例えば、あるジュニアユースの監督さんから「お前のところに○○って選手、練習に行ってるやろ? あいつ獲得するんか?」と言われて「なんでですか?」と訊くと「あいつの親、口出ししてくるので、だいぶややこしいらしいで。監督が息子にあんなこと言った、こんなこと言ったとふれ回っているらしい」と。直接、その選手が所属するチームの監督は言って来ませんが、周辺の人から伝わってきます。
そう言われても、僕には関係ないので良いと思った選手は獲りますが、その選手はかわいそうですよね。親が指導に口出しをすると、結局子どもが損してしまうんです。
親のプレッシャーが嫌で、指導者が関わらなかったり、気を使って指導をしても成長できません。結果、性格的にあまちゃんになって、頑張りがきかない。ちょっとうまくいかないと、プレーがダメになったり。試合に出られないことに慣れていなくて、ふてくされてしまったり。そんな時期を過ごしてしまうと、高校や大学など、親が出て行けない環境になった時に、頭打ちになってしまうんです。自分で自分を高めていく術を持っていないので、どうすればいいかがわからない。親がカーナビになったツケが回ってくるんです。
子どもに間違っていない道を行かそうとした結果、ナビがなくなった時にどの道を行けばいいかがわからなくなってしまうんです。どの道を通ったのか、目的地に着くまでに何があったのか。その経験が血となり肉となるわけです。うまくいかない時に、どうやって解決するか。乗り越えていくかを学ぶのは、サッカーに限らず人生でも重要なこと。高校生はそれをサッカーの中で体験しているわけです。
そう考えると、親が出て行って、障害を取り除いてあげる必要はまったくないのです。
※この記事は「興國高校式Jリーガー育成メソッド ~いまだ全国出場経験のないサッカー部からなぜ毎年Jリーガーが生まれ続けるのか?~」(竹書房・刊)より抜粋したものです。
ーーーーーーーーーーーーー
指導者も保護者にも勉強になる記事です。
読んでみてください!
https://www.sakaiku.jp/column/thought/2019/013901.html
@ーーーーーーーーーーーーー
【親の言動が子どものチャンスを潰している! Jリーガーを続々生み出すサッカー部監督が語る、プロになる子の親の「共通点」】
全国大会の出場経験がないにも関わらず、毎年のようにJリーガーが誕生する興国高校(大阪)。監督を務める内野智章さんに「子どもをプロ選手にするために、保護者がすべきこと」について聞きました。
全国大会出場経験がないにも関わらず毎年のようにJリーガーが誕生する興国高校サッカー部
■保護者は子どものカーナビにならない
興國サッカー部は入部時に、1年生と保護者を集めて「入部前説明会」を行います。この場では部の説明やサッカースタイルなどの話をするのですが、僕が保護者の方に言うのが「息子さんのカーナビになっていませんか?」ということです。
カーナビ通りに行けば、目的地に簡単に着くでしょう。でもそれが、息子さんにとって本当にベストな道なのでしょうか? 道を間違えることによって、より良い道を覚えるのではないでしょうか?
道を間違って、行き止まりになったときに「こっちちゃうわ。あっちの道に行こう」というのも経験です。保護者は子どもより経験があるぶん、「こっちに行ったほうがいい」とアドバイスができますが、その指示通りに動いていても、経験値が溜まらないですよね。カーナビに頼っていたら、道をまったく覚えないのと同じです。しまいには、カーナビがないとどこにも行けなくなる。そんな子どもにしたいのでしょうか?
渋滞にはまったり、事故で道がふさがったときに、カーナビに頼っていては前に進めません。ナビには無い抜け道を瞬時に思いつき、「この道で行けば大丈夫」と思えるかどうか。
そのためには普段から自分で考えて行動して、経験を積み重ねていくしかないんです。
保護者がすべきは、東京に行きたいのに、九州の方を向いて走っていたら「おい、そっちちゃうで」と教えてあげるぐらいでいいんです。大阪から東京に行くのに、中央道で行こうが、新東名で行こうが、どちらでもいい。そこは子どもに任せましょう。でも、山陽道を走っていたら「そっちちゃうで」と。
極端な話、大阪から新潟経由で日本海を回っても、東京に着きますからね。めっちゃ時間かかりますけど(笑)。軌道修正するべきは、子どもが目標から真反対を向いている時。それ以外は口出しせず、基本的には放っておくぐらいでいいのではないでしょうか。
■子どもの不満を聞いてあげる
息子さんの試合を見に来るのは大歓迎。保護者にも「見に来てあげてください」と言っていますが「サッカーのことに関しては、あまり言わないであげてください」と念を押しています。
それよりも、息子さんが、僕ら指導スタッフに不満があるのであれば、文句を聞いてあげてください。そこで、「そうなんや、大変やな、頑張りや」と言ってあげるだけで、ガス抜きになりますから。
そこで一番やってはいけないのが、子どもと一緒に指導スタッフの文句を言うこと。そうなると、軌道修正ができないので伸びません。「監督にそんなこと言われたんか。大変やな」と聞いてあげて、どうしても我慢できなければ、子どもの知らないところで、僕に直接意見を言いに来て下さい。
ただ、誤解してほしくないのは、あなたの子どものために興國サッカー部があるのではないということです。チームの理想を追求するために選手がいて、僕はその理想を追求するために、チームのプレーモデルをより高いレベルで実行できる選手を選ぶわけです。そこで、「いや、私の理想はこうだから」と選手や保護者から言われても、僕にはどうすることもできません。
保護者は子どものサポーターでいてあげてほしいと思います。負けている時はめっちゃ応援して、勝ったらめっちゃ喜ぶ。いいサポーターになってください。評論家はいりません。保護者が評論家になって「監督のサッカーはこうだから」と言い出すと、子どもも頭でっかちになって、現実から目をそむけてしまうんです。
自分の技術や努力が足りていないのに、監督のせいにしてふてくされてもいいことないですよね。社会に出たときに、上司は選べません。でも、自分で入りたくてその会社の面接を受けたわけですよね。それならば、どうすれば上司に認められるか、自分に求められているものはなにかを考えながら、努力をしていくしかないんです。
■プロに進む選手の保護者に共通すること
興國からプロに行った選手の家庭に共通しているのは、保護者が明るくて、試合をよく見に来てくれていたことです。すごく応援し、サッカーのことについては一切口出しをしませんでした。僕とも友好的にコミュニケーションをとりますし、こちらからしない限り、サッカーの話はしません。「監督、元気? いろいろ大変やね」みたいな感じで、世間話をしてケラケラ笑っています。
たまに僕が「ちょっと、おたくの息子さん、僕のことなめてますよ。この前、こんなこと言われたんですけど(笑)」とかフランクに話して「あら、すんません。私からも言っておきますんで」みたいな。これも大阪のノリですよね。
ただ、子どもが入学する前には、すごく熱心に質問をする方もいます。進路のことやケガをしたときにどうするのかなど、親の立場として心配なこともありますからね。でも、入学した後には一切言ってきません。プロに行く選手、大学で活躍する選手の保護者は、 99 %そのタイプです。
なかには自分も若い頃はサッカーをしていて、詳しいお父さんもいます。僕に対して、言いたいこともあるのではと思いますが、ほとんど何も言ってきません。「いつもありがとうございます」みたいな感じで、僕も「こちらこそ、ありがとうございます」というようなスタンスですね。
だから、僕としても選手に気を使わずに指導ができるんです。「こんなことを言ったら、親からクレームが来るかな?」と少しでも頭をよぎったら、言葉を選んでしまいますよね。そうすると指導するタイミングを逃すし、こっちの本気も伝わりきらないんです。
ガツンとぶつかることができると、遠慮なく言えるし、深く関わることができます。だから、選手も本気になってくれるんだと思います。
■親の言動で子どものチャンスが潰れる
才能がある選手の中に、親の関わりによってダメになる子はたくさんいます。例えば、あるジュニアユースの監督さんから「お前のところに○○って選手、練習に行ってるやろ? あいつ獲得するんか?」と言われて「なんでですか?」と訊くと「あいつの親、口出ししてくるので、だいぶややこしいらしいで。監督が息子にあんなこと言った、こんなこと言ったとふれ回っているらしい」と。直接、その選手が所属するチームの監督は言って来ませんが、周辺の人から伝わってきます。
そう言われても、僕には関係ないので良いと思った選手は獲りますが、その選手はかわいそうですよね。親が指導に口出しをすると、結局子どもが損してしまうんです。
親のプレッシャーが嫌で、指導者が関わらなかったり、気を使って指導をしても成長できません。結果、性格的にあまちゃんになって、頑張りがきかない。ちょっとうまくいかないと、プレーがダメになったり。試合に出られないことに慣れていなくて、ふてくされてしまったり。そんな時期を過ごしてしまうと、高校や大学など、親が出て行けない環境になった時に、頭打ちになってしまうんです。自分で自分を高めていく術を持っていないので、どうすればいいかがわからない。親がカーナビになったツケが回ってくるんです。
子どもに間違っていない道を行かそうとした結果、ナビがなくなった時にどの道を行けばいいかがわからなくなってしまうんです。どの道を通ったのか、目的地に着くまでに何があったのか。その経験が血となり肉となるわけです。うまくいかない時に、どうやって解決するか。乗り越えていくかを学ぶのは、サッカーに限らず人生でも重要なこと。高校生はそれをサッカーの中で体験しているわけです。
そう考えると、親が出て行って、障害を取り除いてあげる必要はまったくないのです。
※この記事は「興國高校式Jリーガー育成メソッド ~いまだ全国出場経験のないサッカー部からなぜ毎年Jリーガーが生まれ続けるのか?~」(竹書房・刊)より抜粋したものです。
ーーーーーーーーーーーーー
2019年02月05日
静岡学園サッカー部[谷田 虎の穴]から
僕の好きなコラムの一つ、
静岡学園サッカー部の
『谷田 虎の穴』
https://blogs.yahoo.co.jp/abcd5963ne2/MYBLOG/yblog.html
から、、
指導者も親も含めて大人のあるべき姿像について、是非読んでみてください。
@ーーーーーーーーーーーーーーー
我が子を頑張る大人に育てたいなら 何をほめるか?
「歯を食いしばって正面からぶつかる」素敵な子になってほしい。
「目標に向かって進む」若者になるよう願っている。
ではどうするか?
口が裂けても「うちの子は~」と挑戦者を自慢のネタに使わないこと。ましてや自分の子をSNSで載せて世界中にその軽率さを披露しないこと。
子供を、 他人と比べないこと。他人を妬まないこと。
針小棒大に身内を美化しないこと。自分で勝手な評価をしないこと。
噂で生きないこと。冷厳な現実で生きること。
人の評価はまわりが下すモノ。
自分の浅はかな思いは口をつぐむこと。
それは人としてみっともないことを理解すること。
妄想や噂は幻想であって現実にはならぬ事を理解する事。
身内の勝手な評価は自慢か、勘違いか、もしくは妄想です。
身内の評価はその立ち位置が常に願望と主観であり、
歪められた現実、都合よく構築された虚構の場所である。
そうはっきりと心すること。
親の身勝手な美化された評価は、子が現実を受け止め進む障害、桎梏となり、彼の未来を暗いものとする。
誇れる子を育てるためには、まわりに尊敬されるたしなみと謙虚さと重さを持った大人が絶対不可欠なのです。
立派な御子息を持つ親御さんは例外なく自分の息子の話題は口にしない。
これ真理。
立派な紳士は例外なく自分の妻を誉める。
これも真理。
ほめて育てるというが。
何を誉めるかだ。
運動能力が高い・頭がよくいい成績と「才能」と「結果」を褒めると、必ず「失敗を恐れる」ようになる。
頑張った・毎日諦めない姿勢は素晴らしいと「苦難」と「挑戦」を誉めると、「チャレンジし、諦めない」事を求めるようになる。
では誰が誉めるか 日頃頑張っていない男は誉めても逆効果だ。
ヤンキーにカッコイイですと言われているのと同じだ。
彼の尊敬する人が誉めることが財産になる。
子を育てるのは大人が「尊敬される人生を歩む」こと。
その姿を見せる事。
器が大きく正義漢で男らしく勝負する父。
天使のように愛情深き思慮深い母。
…
…
…ハードルあげすぎた(爆笑)
ーーーーーーーーーーーーー
静岡学園サッカー部の
『谷田 虎の穴』
https://blogs.yahoo.co.jp/abcd5963ne2/MYBLOG/yblog.html
から、、
指導者も親も含めて大人のあるべき姿像について、是非読んでみてください。
@ーーーーーーーーーーーーーーー
我が子を頑張る大人に育てたいなら 何をほめるか?
「歯を食いしばって正面からぶつかる」素敵な子になってほしい。
「目標に向かって進む」若者になるよう願っている。
ではどうするか?
口が裂けても「うちの子は~」と挑戦者を自慢のネタに使わないこと。ましてや自分の子をSNSで載せて世界中にその軽率さを披露しないこと。
子供を、 他人と比べないこと。他人を妬まないこと。
針小棒大に身内を美化しないこと。自分で勝手な評価をしないこと。
噂で生きないこと。冷厳な現実で生きること。
人の評価はまわりが下すモノ。
自分の浅はかな思いは口をつぐむこと。
それは人としてみっともないことを理解すること。
妄想や噂は幻想であって現実にはならぬ事を理解する事。
身内の勝手な評価は自慢か、勘違いか、もしくは妄想です。
身内の評価はその立ち位置が常に願望と主観であり、
歪められた現実、都合よく構築された虚構の場所である。
そうはっきりと心すること。
親の身勝手な美化された評価は、子が現実を受け止め進む障害、桎梏となり、彼の未来を暗いものとする。
誇れる子を育てるためには、まわりに尊敬されるたしなみと謙虚さと重さを持った大人が絶対不可欠なのです。
立派な御子息を持つ親御さんは例外なく自分の息子の話題は口にしない。
これ真理。
立派な紳士は例外なく自分の妻を誉める。
これも真理。
ほめて育てるというが。
何を誉めるかだ。
運動能力が高い・頭がよくいい成績と「才能」と「結果」を褒めると、必ず「失敗を恐れる」ようになる。
頑張った・毎日諦めない姿勢は素晴らしいと「苦難」と「挑戦」を誉めると、「チャレンジし、諦めない」事を求めるようになる。
では誰が誉めるか 日頃頑張っていない男は誉めても逆効果だ。
ヤンキーにカッコイイですと言われているのと同じだ。
彼の尊敬する人が誉めることが財産になる。
子を育てるのは大人が「尊敬される人生を歩む」こと。
その姿を見せる事。
器が大きく正義漢で男らしく勝負する父。
天使のように愛情深き思慮深い母。
…
…
…ハードルあげすぎた(爆笑)
ーーーーーーーーーーーーー
2018年11月16日
Liga MX (メキシコ1部リーグ)ケレタロFCコーチ
Liga MX (メキシコ1部リーグ)
Gallos Blancos de Querétaro (ガジョス ブランコス デ ケレタロ/ケレタロFC)で、U15~U21分析スタッフ等で活躍している友人の塩沢拓也が来長したので、熱いサッカー談義をしてきました。


たくやはもう6年半もメキシコに住み、自身の夢のため、サッカーの指導力向上のために勉強と実践をプロクラブの環境でし続けています。
メキシコでサッカーライセンスを取得し、今ではメキシコ1部リーグのクラブでスタッフとしてプロ契約結びサッカーを仕事に生きています。
メキシコの育成年代の話しから、たくやが在籍した2チームでの育成哲学の話、仕事として行なっているサッカーの試合分析から育成分析、指導方法などの話を聞き、ノザワナの試合を一緒に観ながら様々な観点からサッカーを解説してくれました。
サッカーの新しい見解や、忘れていた大切なもの、より細かく深く掘り下げる基本の大切さから、その後の発展、応用方法...等々、、
昼過ぎから深夜まで本当に熱心にたくさんの気付きを教えてくれました。
この気付きをクラブの選手達のためにたくさん活かしていきます!!
たくやどうもありがとう!!!
次はノザワナにも顔を出してくれると思うので皆さん楽しみにしていてください。

終わったあと写真撮り忘れていたので明るいスーパーで撮りました(笑)
Gallos Blancos de Querétaro (ガジョス ブランコス デ ケレタロ/ケレタロFC)で、U15~U21分析スタッフ等で活躍している友人の塩沢拓也が来長したので、熱いサッカー談義をしてきました。


たくやはもう6年半もメキシコに住み、自身の夢のため、サッカーの指導力向上のために勉強と実践をプロクラブの環境でし続けています。
メキシコでサッカーライセンスを取得し、今ではメキシコ1部リーグのクラブでスタッフとしてプロ契約結びサッカーを仕事に生きています。
メキシコの育成年代の話しから、たくやが在籍した2チームでの育成哲学の話、仕事として行なっているサッカーの試合分析から育成分析、指導方法などの話を聞き、ノザワナの試合を一緒に観ながら様々な観点からサッカーを解説してくれました。
サッカーの新しい見解や、忘れていた大切なもの、より細かく深く掘り下げる基本の大切さから、その後の発展、応用方法...等々、、
昼過ぎから深夜まで本当に熱心にたくさんの気付きを教えてくれました。
この気付きをクラブの選手達のためにたくさん活かしていきます!!
たくやどうもありがとう!!!
次はノザワナにも顔を出してくれると思うので皆さん楽しみにしていてください。

終わったあと写真撮り忘れていたので明るいスーパーで撮りました(笑)
2018年06月16日
ワールドカップ観戦の仕方‼︎









NHKワールドカップのアプリを使って、ワールドカップ観せてあげてください!
色んな角度からのゴールシーンはサッカーを超面白く観れるし、選手の全体の動きを俯瞰で観れる戦術カメラは、今練習でやってる「FWの狙いとボールの受け方」「サイドハーフの狙いとボールの受け方」「ボランチの狙いと受け方」「センターバックとゴールキーパーの狙いと受け方」がとても解り易く、観易く、どんなチームの試合も面白く観ることができます!!
また、シュート、ファール、走行距離、アシスト、パス成功率等のスタッツが見れることも面白いです!
オススメは、テレビ観ながら、NHKアプリも使って観ることです!!
是非是非、選手達にNHKアプリを使って観せてあげてください!
https://www.google.co.jp/amp/s/rocketnews24.com/2018/06/15/1077848/amp/
https://www1.nhk.or.jp/sports/2018fifaworldcup/app/
2018年02月20日
【2/20キャスクスピードトレーニング】

【キャスクスピードトレーニング】
サッカー以外のスポーツの選手や他のチームの選手などと切磋琢磨してがんばっています!!
ノザワナFCの選手は多いですが他のチームの選手『大募集』です!
今日はキャスクスピードトレーニング長野校が行われました。
今日は『スタート』と『加速』をテーマでやりました。
スタートでは頭の位置、スタートの基本姿勢、前傾姿勢は意識しました。今回特に意識したのは二軸スタートです。二軸スタートとはモデル歩きみたいな一本の線の上を走るのではなくスタート時は2本の線の上を走るということです。なのでマーカーを置き自然に二軸スタートが出来るようにしました。
そして加速をし、トップスピードになったら二軸から一軸にするようにします。
最後に、まだ『120%』を出しきれない選手が多いです。指導者側も大きい声を出してもっともっとみんなで切磋琢磨出来る環境をつくっていきたいです。
《池田》
【体験のお申込みはこちら】
キャスクスピードトレーニングHP
http://casq.jp/sp/
#キャスクスピードトレーニング
#CASQスピードトレーニング
#長野校
#NOZAWANAFC #ノザワナFC #長野少年サッカー #長野少年サッカーチーム #長野少年サッカースクール #長野少年サッカークラブ #スペインサッカー #FCバルセロナ #サッカー上達 #夢はサッカー選手 #サッカー選手になりたい #nozawana #少年サッカー #子育て
2018年02月17日
【2月17日鎌田TM】
今日は鎌田サッカースポーツ少年団と練習試合をさせてもらいました!
寒い中でしたが準備などありがとうございました。
今日も前回と同じく『相手を見てどこから攻めるかを判断する』というのをテーマにしました。
ボールをもっていない時に見ることが大切です。
どこから攻めればいいかというのを考えるのも大切ですが「相手の逆」(相手の狙っていないとこ)をとるのが大切です。
それらは相手を見なければできません。なので相手を見てプレーしましょう!
《池田》
===================
ノザワナFCでは、選手1人1人を絶対に上手くさせます。
FCバルセロナスクールやスペイン研修など積んだ経験を基に、現場の子ども達に合わせたカリキュラムと指導方法で、選手1人1人を必ず上手くさせます!
《体験のお申込みはこちら》
☆年中〜小学2年生 初心者大歓迎
★3〜6年生
[Tel&Fax] 026-477-2723
[Mail] NOZAWANA.FC@gmail.com(@を半角に)
[携帯] 090-3130-9783(代表 勝山)
[HP]
http://nozawanafc.com
[ノザワナスクールblog]
http://nozawanafc.naganoblog.jp
#サッカーが絶対に上手くなる #NOZAWANAFC #ノザワナFC #長野少年サッカー #長野少年サッカーチーム #長野少年サッカースクール #長野少年サッカークラブ #スペインサッカー #FCバルセロナ #サッカー上達 #夢はサッカー選手 #サッカー選手になりたい #nozawana #少年サッカー #子育て #キャスクスピードトレーニング長野校もやってます。
寒い中でしたが準備などありがとうございました。
今日も前回と同じく『相手を見てどこから攻めるかを判断する』というのをテーマにしました。
ボールをもっていない時に見ることが大切です。
どこから攻めればいいかというのを考えるのも大切ですが「相手の逆」(相手の狙っていないとこ)をとるのが大切です。
それらは相手を見なければできません。なので相手を見てプレーしましょう!
《池田》
===================
ノザワナFCでは、選手1人1人を絶対に上手くさせます。
FCバルセロナスクールやスペイン研修など積んだ経験を基に、現場の子ども達に合わせたカリキュラムと指導方法で、選手1人1人を必ず上手くさせます!
《体験のお申込みはこちら》
☆年中〜小学2年生 初心者大歓迎
★3〜6年生
[Tel&Fax] 026-477-2723
[Mail] NOZAWANA.FC@gmail.com(@を半角に)
[携帯] 090-3130-9783(代表 勝山)
[HP]
http://nozawanafc.com
[ノザワナスクールblog]
http://nozawanafc.naganoblog.jp
#サッカーが絶対に上手くなる #NOZAWANAFC #ノザワナFC #長野少年サッカー #長野少年サッカーチーム #長野少年サッカースクール #長野少年サッカークラブ #スペインサッカー #FCバルセロナ #サッカー上達 #夢はサッカー選手 #サッカー選手になりたい #nozawana #少年サッカー #子育て #キャスクスピードトレーニング長野校もやってます。