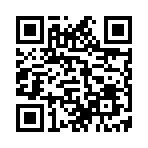2017年02月27日
スペイン遠征9日目
スペイン遠征9日目









サンクガット大会
サッカー会場はただのサッカー大会といった雰囲気ではなく、もう街の『お祭り』の様な異様な雰囲気です。
強そうな気合の入った顔をしているスパイン人たちがわんさかわんさかいて、ロッカールームに案内されて、ローッカールームまでの道のりを通るだけで緊張していくのが伝わります。
ロッカールームに案内されて、綺麗すぎるロッカールームに、廊下にはバルサやエスパニョールのジャージを着た選手スタッフ達がもの珍しそうに日本人の僕達を見ています。
もう、ロッカールーム閉じ込められているだけで、息が詰まりそうな雰囲気が伝わってきました。。汗
顔も真っ青だったので、早くグラウンドに出て体を動かした方が良いと思い、外にましたが、外にはとてもたくさんの応援団、外国人の保護者達がいて、グラウンドに出ても息が詰まりそうな雰囲気が伝わってきます。
大きい声を出すWUPをやっても腹の底から大きい声は出ません。。
体を動かしても重たそう。。
鈍い。。
どうにかして、緊張をほぐしたいと思いましたが、何をやってもうまくいかないまま試合が始まりました。。
第1試合
vs Mastic ManresaA(ナスティックマレンサA)
0-5●
第2試合
vs ManlleuA(マンジェウA)
0-3●
第3試合
vs Sant CugatB(サンクガットB)
0-7●
第4試合
vs FC BarcelonaA(FCバルセロナA)
0-12●
9-10位決定戦
vs ASL Japan selection(ASLJ選抜)
1-0 ○
(トーマ)
カタルーニャ州のサッカーのレベルの高さ、街クラブのレベルの高さを思いっきり体感させられました。。
サッカーは先ず第一に戦術じゃない、『個人の能力だ!!』と、
個人の能力は、『サッカーに立ち向かう意欲の差だ!!』と、
サッカーは『戦うものだ!!!』と。
戦うことを恐がらない、
自ら好んで戦いに行く、
自分の役割以上のことを行う、
サッカーの中での仕事をきっちり行う!!
といった、
サッカーとはどういうものか?
何をしなくてはいけないのか?
といった、最低限の基準、レベル、意識がとても高く感じました。
これくらいでいいだろう。。
と、
こんなもんじゃダメだ!!もっともっとだ!!!
といった個人のメンタルの差もとても感じました。
そして、
試合に立ち向かうスペイン人の意欲、戦う意識と迫力は、隣にいる選手達はビクビクしていたのではないでしょうか。。
WUPは15分程度、それでも試合に入る気持ちの入れ方はとても高くすごい迫力でした。
自分達で鼓舞し合い、大きい声を出し合い気持ちを高め合う、
それが当たり前で、
練習や練習試合と本気度は全く違い、200%を出すんだ!!!といった気合いでした。
もちろん、練習や練習試合でも、意欲と本気度は高く、どんな些細なプレーでも絶対に負けない!!!
という強い気持ちを持って取り組んでいますが、本番のそれは全く異なり、5倍くらいの迫力と気合いとパワーでした。
そしてスペイン人は、試合への向かい方、気持ちの高め方、気持ちの持ち方、試合に入る時のテンションを、
とてもとてもとても大切にしていることが伝わってきました。
アップは15分程度、なのに試合では立ち上がりからエンジン全開!!!
練習や練習試合に強いノザワナと、
『本番が1番強い』スペイン人の選手達を感じました。
それは、闘争心と、試合に向かう気持ちの持ち方、気合いの入れ方、テンションの高め方が、とても大切で、本気になって試合に立ち向かう選手達の本気を感じました。
整列して選手入場する時の隣にいるスペイン人達の迫力といったら、選手達はどう感じていたでしょうか?良いものはとことん徹底的にパクりたいですが、あの闘争心を表現することはできるでしょうか。。
どうにかあの闘争心と、それを表現できる自信とメンタルと表現力を身に付けたいと思いますが、こればっかりは本人が最終的にどこまで望むか?によって変わってくると思います。
よっっぽどの強い気持ちで望まない限り、あの闘争心を出すことは簡単にはできないと思います。
日本人には日本人の戦う時の気持ちや、気持ちのもっていき方や、戦う姿勢や、良さを、探求していけば見付かるかもしれません。
だけど、今は何ももっていませんでした。
そして、日本人の持っている答え、何を求めたら良いのかも僕は分かりませんでした。
武士道?武道の精神?侍の精神?農耕民族の精神?相撲?柔道、合気道、空手とか?戦争のカミカゼ特攻隊?
柔道とか相撲は国技で、『絶対に負けられない!!』っていう強い気持ちで戦うのかもしれません。
戦う前は、ワーワー言いませんが精神統一してやるのが良いのかもしれません。
サッカーもそれが合うのか?サッカーは違うのか?日本人には何が合うのか?サッカーには何が合うのか?
僕は答えを持っていませんので、
そこを探求していく必要もあるのかもしれません。
色々良いものはやってみて、計っていこうと思います。
日本人のみんなが本気で望み、本気で変われることを信じてサポートしていきたいと思います。
また、日本人はテクニックはあるけど、、みたいな話をよく聞きますが、テクニックも全く足りないと感じました。
ノザワナの選手達のテクニックはとても足りないと感じました。
先ず、ボールを受けれない、
ボールが来てもボールが収まらない、
ボールが来ても後ろにトラップするのがやっと、
中には足元からちょっとズレるとトラップのできない選手もいます、
そして、
ボールを持っても仕掛けられない、
仕掛けるボールの持ち方ができない、
仕掛ける自分のドリブルをそもそも持っていない、
自分はどこにボールを置けば仕掛けられるのか、
自分の得意なボールの置き場所はどこか?
シュートやキックの威力、精度もとても高く、
めちゃくちゃドリブルもトラップもキックもシュートも判断も選択肢もテクニックのレベルが高かったです。
個々のテクニックの部分、、
また、それを発揮する判断のスピード、
というかそもそも仕掛ける選択肢や、複数の選択肢を持てる選手が少ない。
等々、クラブとして指導者として全てを見直さなければいけないと感じました。
そして、選手達が家で、自分で、本気になって取り組まなければいけないこともとても多くあることに気付いたと思います。
これには、ご家庭でのサポート必要不可欠なレベルです。
食事の面から、自主練のサポートや内容から、情報、様々な体験、刺激、、等々
また、サッカーの試合を良く観ています。
大人と同じようなことをプレベンハミン(1年生、2年生の早生まれ)から平気でやります。
例えば、ゴール近くの関節フリーキックでは、壁に入った7歳の1年生の選手達が、ジリジリと前に出て来ます。近距離での関節フリーキックを、ボールが動いた瞬間に飛び込んで、近距離から顔面ブロックしにいきます。
例えば、ボールを取られた瞬間に後ろからでも足を伸ばし必ずボールを簡単に取られないように奪い返しにいきます。直ぐに後ろから足を伸ばし必ずボールに触ります。そして自分がボールを奪われてカウンター喰らうなんてことがないようにほとんどの選手が足を伸ばしてボールに触ってカウンターを止めます。そのスピードと強さと迫力はとても1年生には見えません。
例えば、1年生でも体のデカイ相手には腕と体全体を駆使しして相手をブロックします。
腕の使い合いや、身体全身の使い方はとても1年生にはみえません。
とてもたくさんの大人のサッカーを観ているのだと思います。
やろうとしているサッカーは、とても激しく強く、逞しく、大人のサッカーを1年生から戦っています。
コートは大人のコートの半分のコートで7人制を年長さん1年生の年齢から平気で戦いサッカーをしています。
なので、ダイナミックによく走るし、キックも強いしよく飛ぶし、コンタクトも強いし、逞しくタフに走ってサッカーを戦います。
大人のレベルの高い、質の高いサッカーを小さい頃からよく観ているのがよく分かります。
カタルーニャのサッカーのレベルの高さを痛感しました。
これからみんながどこまで望み、どこまで本気になって、どこまで成長できるのか。
そして、そのためのサポートも、
こちらもあきらめずに、高くを望み、成長を信じて、本気になって取り組んでいきます。









サンクガット大会
サッカー会場はただのサッカー大会といった雰囲気ではなく、もう街の『お祭り』の様な異様な雰囲気です。
強そうな気合の入った顔をしているスパイン人たちがわんさかわんさかいて、ロッカールームに案内されて、ローッカールームまでの道のりを通るだけで緊張していくのが伝わります。
ロッカールームに案内されて、綺麗すぎるロッカールームに、廊下にはバルサやエスパニョールのジャージを着た選手スタッフ達がもの珍しそうに日本人の僕達を見ています。
もう、ロッカールーム閉じ込められているだけで、息が詰まりそうな雰囲気が伝わってきました。。汗
顔も真っ青だったので、早くグラウンドに出て体を動かした方が良いと思い、外にましたが、外にはとてもたくさんの応援団、外国人の保護者達がいて、グラウンドに出ても息が詰まりそうな雰囲気が伝わってきます。
大きい声を出すWUPをやっても腹の底から大きい声は出ません。。
体を動かしても重たそう。。
鈍い。。
どうにかして、緊張をほぐしたいと思いましたが、何をやってもうまくいかないまま試合が始まりました。。
第1試合
vs Mastic ManresaA(ナスティックマレンサA)
0-5●
第2試合
vs ManlleuA(マンジェウA)
0-3●
第3試合
vs Sant CugatB(サンクガットB)
0-7●
第4試合
vs FC BarcelonaA(FCバルセロナA)
0-12●
9-10位決定戦
vs ASL Japan selection(ASLJ選抜)
1-0 ○
(トーマ)
カタルーニャ州のサッカーのレベルの高さ、街クラブのレベルの高さを思いっきり体感させられました。。
サッカーは先ず第一に戦術じゃない、『個人の能力だ!!』と、
個人の能力は、『サッカーに立ち向かう意欲の差だ!!』と、
サッカーは『戦うものだ!!!』と。
戦うことを恐がらない、
自ら好んで戦いに行く、
自分の役割以上のことを行う、
サッカーの中での仕事をきっちり行う!!
といった、
サッカーとはどういうものか?
何をしなくてはいけないのか?
といった、最低限の基準、レベル、意識がとても高く感じました。
これくらいでいいだろう。。
と、
こんなもんじゃダメだ!!もっともっとだ!!!
といった個人のメンタルの差もとても感じました。
そして、
試合に立ち向かうスペイン人の意欲、戦う意識と迫力は、隣にいる選手達はビクビクしていたのではないでしょうか。。
WUPは15分程度、それでも試合に入る気持ちの入れ方はとても高くすごい迫力でした。
自分達で鼓舞し合い、大きい声を出し合い気持ちを高め合う、
それが当たり前で、
練習や練習試合と本気度は全く違い、200%を出すんだ!!!といった気合いでした。
もちろん、練習や練習試合でも、意欲と本気度は高く、どんな些細なプレーでも絶対に負けない!!!
という強い気持ちを持って取り組んでいますが、本番のそれは全く異なり、5倍くらいの迫力と気合いとパワーでした。
そしてスペイン人は、試合への向かい方、気持ちの高め方、気持ちの持ち方、試合に入る時のテンションを、
とてもとてもとても大切にしていることが伝わってきました。
アップは15分程度、なのに試合では立ち上がりからエンジン全開!!!
練習や練習試合に強いノザワナと、
『本番が1番強い』スペイン人の選手達を感じました。
それは、闘争心と、試合に向かう気持ちの持ち方、気合いの入れ方、テンションの高め方が、とても大切で、本気になって試合に立ち向かう選手達の本気を感じました。
整列して選手入場する時の隣にいるスペイン人達の迫力といったら、選手達はどう感じていたでしょうか?良いものはとことん徹底的にパクりたいですが、あの闘争心を表現することはできるでしょうか。。
どうにかあの闘争心と、それを表現できる自信とメンタルと表現力を身に付けたいと思いますが、こればっかりは本人が最終的にどこまで望むか?によって変わってくると思います。
よっっぽどの強い気持ちで望まない限り、あの闘争心を出すことは簡単にはできないと思います。
日本人には日本人の戦う時の気持ちや、気持ちのもっていき方や、戦う姿勢や、良さを、探求していけば見付かるかもしれません。
だけど、今は何ももっていませんでした。
そして、日本人の持っている答え、何を求めたら良いのかも僕は分かりませんでした。
武士道?武道の精神?侍の精神?農耕民族の精神?相撲?柔道、合気道、空手とか?戦争のカミカゼ特攻隊?
柔道とか相撲は国技で、『絶対に負けられない!!』っていう強い気持ちで戦うのかもしれません。
戦う前は、ワーワー言いませんが精神統一してやるのが良いのかもしれません。
サッカーもそれが合うのか?サッカーは違うのか?日本人には何が合うのか?サッカーには何が合うのか?
僕は答えを持っていませんので、
そこを探求していく必要もあるのかもしれません。
色々良いものはやってみて、計っていこうと思います。
日本人のみんなが本気で望み、本気で変われることを信じてサポートしていきたいと思います。
また、日本人はテクニックはあるけど、、みたいな話をよく聞きますが、テクニックも全く足りないと感じました。
ノザワナの選手達のテクニックはとても足りないと感じました。
先ず、ボールを受けれない、
ボールが来てもボールが収まらない、
ボールが来ても後ろにトラップするのがやっと、
中には足元からちょっとズレるとトラップのできない選手もいます、
そして、
ボールを持っても仕掛けられない、
仕掛けるボールの持ち方ができない、
仕掛ける自分のドリブルをそもそも持っていない、
自分はどこにボールを置けば仕掛けられるのか、
自分の得意なボールの置き場所はどこか?
シュートやキックの威力、精度もとても高く、
めちゃくちゃドリブルもトラップもキックもシュートも判断も選択肢もテクニックのレベルが高かったです。
個々のテクニックの部分、、
また、それを発揮する判断のスピード、
というかそもそも仕掛ける選択肢や、複数の選択肢を持てる選手が少ない。
等々、クラブとして指導者として全てを見直さなければいけないと感じました。
そして、選手達が家で、自分で、本気になって取り組まなければいけないこともとても多くあることに気付いたと思います。
これには、ご家庭でのサポート必要不可欠なレベルです。
食事の面から、自主練のサポートや内容から、情報、様々な体験、刺激、、等々
また、サッカーの試合を良く観ています。
大人と同じようなことをプレベンハミン(1年生、2年生の早生まれ)から平気でやります。
例えば、ゴール近くの関節フリーキックでは、壁に入った7歳の1年生の選手達が、ジリジリと前に出て来ます。近距離での関節フリーキックを、ボールが動いた瞬間に飛び込んで、近距離から顔面ブロックしにいきます。
例えば、ボールを取られた瞬間に後ろからでも足を伸ばし必ずボールを簡単に取られないように奪い返しにいきます。直ぐに後ろから足を伸ばし必ずボールに触ります。そして自分がボールを奪われてカウンター喰らうなんてことがないようにほとんどの選手が足を伸ばしてボールに触ってカウンターを止めます。そのスピードと強さと迫力はとても1年生には見えません。
例えば、1年生でも体のデカイ相手には腕と体全体を駆使しして相手をブロックします。
腕の使い合いや、身体全身の使い方はとても1年生にはみえません。
とてもたくさんの大人のサッカーを観ているのだと思います。
やろうとしているサッカーは、とても激しく強く、逞しく、大人のサッカーを1年生から戦っています。
コートは大人のコートの半分のコートで7人制を年長さん1年生の年齢から平気で戦いサッカーをしています。
なので、ダイナミックによく走るし、キックも強いしよく飛ぶし、コンタクトも強いし、逞しくタフに走ってサッカーを戦います。
大人のレベルの高い、質の高いサッカーを小さい頃からよく観ているのがよく分かります。
カタルーニャのサッカーのレベルの高さを痛感しました。
これからみんながどこまで望み、どこまで本気になって、どこまで成長できるのか。
そして、そのためのサポートも、
こちらもあきらめずに、高くを望み、成長を信じて、本気になって取り組んでいきます。
2017年02月27日
教育、子育てについて
ずっと前から思っていること、感じていることがあって、答えではありませんが色々考えてみました。
持っている力を自分の力で発揮できないもったいない選手や、
ボーッとしてたり、集中力がよく切れたり、危機察知能力(危ないことがなんなのか気付いていない。または危ないところがあるのに全く別のところを守っている。)が薄い選手がいて、どうしたら良くなるんだろうとずっと考えていました。
(※指導者としてクラブで出来ることは別に考えておりますので、下記は各ご家庭で考えてもらうことだと捉えてください。)
試合中に持っている力を自分の力で発揮できなかったり、ボーッとしてたり、集中力がよく切れたり、危機察知能力(危ないことがなんなのか気付いていない。または危ないところがあるのに全く別のところを守っている。)が薄い選手っていうのは、子どもに、冷や汗をかかせるような経験、潜在能力を引き出すような経験が少ないのではないかと思います。
例えば一つの例で言えばスパルタです。スパルタが全て良いとは言いませんが、部分的に厳しくすることはとても必要なことだと思います。優秀な選手の多くは愛情と共に、部分的に親からとても厳しい教育を受けています。スパルタによって子どもが本能的に、潜在的に、危機察知する瞬間でもあると思います。
スパルタをやらなかったとしても、他に子どもの潜在能力を引き出す教育・接し方はあると思います。
例えば親子で一緒に歩く時を想像してみてください。
皆さんは、子どものゆっくりゆっくりなのんびりなペースに合わせますか?
それとも、子どもの持っている力を引き出すために、子どもが歩けるギリギリの速いペースで歩きますか?
それによって、子どもの「潜在能力を引き出す」ことや、「自分の持っている全力を自分から出せる」ようになることに繋がってくると思います。
逆に子どものペースで歩き、のんびりのんびりゆっくり歩くことは、子どもの「潜在能力を引き出せず」、子どもが「持っている力を自分から発揮できない」ことや、「成長を遅らせる」ことに繋がってくると思います。
現在のチームを見ても、今まで関わってきた1000人弱の子供達とそのご家庭を見ても、ほとんどがこういった日常からの子どもの潜在能力を引き出す教育を意識して行なっているか、そうでないか、によって大きく子どもの実力の発揮の仕方が変わってくることは確信しています。
上記は、一つの例に過ぎませんが、例えば、子どもが「冷や汗」をかいて「潜在能力」(持っている全ての力)(もしくは成長するタイミング)を引き出す環境というのは他にもたくさんあると思います。
例えば、
・混雑の人混みの中で手を離す。
子どもが必死になって潜在能力を発揮して一生懸命ついていこうとすると思います。
・迷子。
迷子になって泣いている時間や、どうしようか?どうしようか!?と真剣に考えている時間というのは、子どもが冷や汗をかきながらも潜在能力を発揮して、どうにか解決しようと頭をフル回転させたり、全身のフルパワーを使ってめちゃくちゃ力強く、わんわんと泣くと思います。
子どもが死に物狂いで必死になって解決しようとする、成長するタイミングだと思います。
※※ただこれには絶対に必要な条件があります。
それは「愛が子どもに伝わっている」か、ということです。
上記のことを、子どもに愛が伝わっていない状況でやると、子どもは真っ直ぐに育って行かないと思います。
迷子にするにしても、前提条件として「よそ見してはしてはダメよ!!しっかりついてくるのよ!!」と、必ず子どもに熱心に伝えた上で、子どもがよそ見をしている時に迷子にしてあげる。とか、、
「お母さんは手荷物がいっぱいで手を繋いであげられないけど、しっかりついてくるのよ!!」と言って人混みの中で手を繋がずについて来させる。
等々。。。
上記のことは5年前にスペインに行き、先日イギリスに行った時から感じていることです。
スペインでは、2歳くらいのよちよち歩きの子が、手を叩くお母さんに向かって一生懸命歩いている最中に、転んで石畳に顔をぶつけました。
それなのにお母さんはどうしたかと言うと、、
そんな光景を微笑ましそうにニコニコ微笑みながら、手を叩き続けていました。
そしたら、赤ちゃんはどうしたかと言うと、、、
転んで一瞬泣いたものの、ニコニコ嬉しそうに微笑むお母さんの顔を見て、直ぐに笑顔を取り戻して、もう一度立ち上がって歩いて行きました。
そしてお母さんのところに来た時に、お母さんはめちゃくちゃ褒めてあげて何回もキスしてあげていました。
あぁ〜〜、これだなぁ〜と、、、日本との違いはこういうところから出てるんだなぁと思いました。
日本ではほとんどの多くが間違いなく、
転んだ瞬間に親が真っ青な顔をして手を差し伸べてしまうと思います。
そして、子どもに頑張らせることすらさせる前に、
子どもが自分の力で立ち上がる機会すら与える前に、
「痛かったねぇ、、大丈夫、大丈夫、、」
なでなで、なでなで、、、
だと思います。
これでは、
「潜在能力を引き出す」どころか、
「自立」するどころか、
「自分の力を自分で出すことのできない『甘えん坊』」
になっていくと思います。
よく次男や三男が長男に比べ少し逞しかったりするのは、段々とこういう部分に手を掛けなくなっていくからだと思います。
ですので、一人っ子に対しても、長男に対しても、次男、三男に対しても、潜在能力を引き出す接し方を意識して取り組んであげるべきだと思います。
先日のイギリスで感じたことは、小松さんと一緒に街を歩いてると、小松さんと僕は一緒にランニングしたり、歩いて遠くまで行ったりしていて、とても歩くのが速い方で、この日も意識して早歩きをしていました。
それなのに、前にいる小学4-6年生くらいの男の子と、中学生の女の子と両親の4人家族にいつまで経っても距離が縮まらないことに気づきました。
「相当早く歩いてますね、、小学生の男の子と、中学生の女の子がいるのに、距離が縮まらないなんて、、」
そんな会話から、、たくさんの例や仮説を聞きながら、、
外国では、赤ちゃんの時から寝室が別で、その結果自立を促しやすいんじゃないか?それなのに愛情は恐らく日本より伝わっているだろう。みたいな話や、色んな話を教育学部の准教授と分析をしながら話しました。
結果、僕が感じたのは、小さい時から子どもに合わせるのではなく、子どもを鍛えるために、子どもの潜在能力を発揮するためにも、子どものギリギリの力を引き出そうとしてあげる教育、接し方が違うのだと思いました。
そして、その結果スポーツの中でも違いが生まれてきているのだと感じました。
恐らく子どもは最初はいっぱいいっぱいだと思います。
遅れてしまう、置いてかれてしまう、、と心配しながら冷や汗もかくだろうし、汗もびっしょりかくと思います。
だけど、そんなギリギリの時に子どもは成長していくのだと思います。
子どもの潜在能力を引き出せる時ってそういときなんだと思います。
『ヤバイ!!!!(冷汗)』
って、本気で子どもが感じてる時に、、
頭をフル回転させて、
全身の力を最大限フルに使って、
持っている本当の力を全て発揮してくるんだと思います。
そういう日常の積み重ねが、
自立したり、
持っている力を全て自分の力で出せたり、
自信を持っていたり、
困ったことを自分の力で解決できたりすることに繋がってくると思います。
みなさんのお子さんにはそういう経験をたくさんさせてあげていますか??
力はあるのに、
『自分の持っている力を自分で発揮できない選手』
『困った時に自分の力で解決できない選手』
『危険なことが分かっていない選手』
が、当クラブにはまだまだいます。
今、最も重要視している課題です。
これに関しては、クラブで出来ることもありますが、日常から各ご家庭で意識して取り組んでいただくしかございません。
もちろん、クラブが、僕達指導者がどうにかしてあげられることもあると思いますので、日々模索しています。
ですが、各ご家庭でももっともっと本気になっていただかないと、子どもの本当の成長は見込めません。
『クラブに預けとけばなんとかなる』という考えではなんとかなりません!!!!
そういった印象を持つご家庭もとても多いです。
クラブで関われる時間は僅かな時間で、みんなが同じ練習をしていて、その中でも成長の差が大きく出ています。
クラブ内で成長の差が出ていますが、他の選手に差をつけている選手は、何が違うのか??親ももっともっと本気になって考えるべきだと思います。
子どもとクラブに任せて放ったらかしでも良いのかも知れません。
けど、今成長してほしい、試合で活躍して良い経験を積んでほしい、と願うなら、子どもとクラブに任せっきりよりも、親も良く考えて本気になって力強くサポートしていくことが必要だと思います。
そして、当クラブ内でもそういう親子が、試合で力を発揮できていることにもっと目を向けるべきだと思います。
活躍しているなりの理由が必ずあります。
3年生で新しく入ってきて、4年生の試合に出てもとても活躍しているA君のお父さんに聞くと、2年生の時から体幹トレーニングを毎日1種類からさせ始めて、今ではお父さんがやらせなくても毎日8種類の体幹トレーニングを欠かさず行っているようです。
また、食事にも相当意識をされていて、小さいころから意識して取り組んできた食事の成果が3年生の現時点で既に大きな成果として出ていると言えます。
自分のお子さんが本当に潜在能力を、「自分の力で発揮できているか?」よく見てみてください。
力を出せていないと感じるのであれば、ご家庭でももっともっと本気になって取り組んでいただくことが、子どもの本当の成長を促します。
クラブでも僕達指導者も、模索していきます。
保護者-選手-クラブ(指導者)が、三位一体となって、本当に力強い子どもの育成をしていくことが必須です。
持っている力を自分の力で発揮できないもったいない選手や、
ボーッとしてたり、集中力がよく切れたり、危機察知能力(危ないことがなんなのか気付いていない。または危ないところがあるのに全く別のところを守っている。)が薄い選手がいて、どうしたら良くなるんだろうとずっと考えていました。
(※指導者としてクラブで出来ることは別に考えておりますので、下記は各ご家庭で考えてもらうことだと捉えてください。)
試合中に持っている力を自分の力で発揮できなかったり、ボーッとしてたり、集中力がよく切れたり、危機察知能力(危ないことがなんなのか気付いていない。または危ないところがあるのに全く別のところを守っている。)が薄い選手っていうのは、子どもに、冷や汗をかかせるような経験、潜在能力を引き出すような経験が少ないのではないかと思います。
例えば一つの例で言えばスパルタです。スパルタが全て良いとは言いませんが、部分的に厳しくすることはとても必要なことだと思います。優秀な選手の多くは愛情と共に、部分的に親からとても厳しい教育を受けています。スパルタによって子どもが本能的に、潜在的に、危機察知する瞬間でもあると思います。
スパルタをやらなかったとしても、他に子どもの潜在能力を引き出す教育・接し方はあると思います。
例えば親子で一緒に歩く時を想像してみてください。
皆さんは、子どものゆっくりゆっくりなのんびりなペースに合わせますか?
それとも、子どもの持っている力を引き出すために、子どもが歩けるギリギリの速いペースで歩きますか?
それによって、子どもの「潜在能力を引き出す」ことや、「自分の持っている全力を自分から出せる」ようになることに繋がってくると思います。
逆に子どものペースで歩き、のんびりのんびりゆっくり歩くことは、子どもの「潜在能力を引き出せず」、子どもが「持っている力を自分から発揮できない」ことや、「成長を遅らせる」ことに繋がってくると思います。
現在のチームを見ても、今まで関わってきた1000人弱の子供達とそのご家庭を見ても、ほとんどがこういった日常からの子どもの潜在能力を引き出す教育を意識して行なっているか、そうでないか、によって大きく子どもの実力の発揮の仕方が変わってくることは確信しています。
上記は、一つの例に過ぎませんが、例えば、子どもが「冷や汗」をかいて「潜在能力」(持っている全ての力)(もしくは成長するタイミング)を引き出す環境というのは他にもたくさんあると思います。
例えば、
・混雑の人混みの中で手を離す。
子どもが必死になって潜在能力を発揮して一生懸命ついていこうとすると思います。
・迷子。
迷子になって泣いている時間や、どうしようか?どうしようか!?と真剣に考えている時間というのは、子どもが冷や汗をかきながらも潜在能力を発揮して、どうにか解決しようと頭をフル回転させたり、全身のフルパワーを使ってめちゃくちゃ力強く、わんわんと泣くと思います。
子どもが死に物狂いで必死になって解決しようとする、成長するタイミングだと思います。
※※ただこれには絶対に必要な条件があります。
それは「愛が子どもに伝わっている」か、ということです。
上記のことを、子どもに愛が伝わっていない状況でやると、子どもは真っ直ぐに育って行かないと思います。
迷子にするにしても、前提条件として「よそ見してはしてはダメよ!!しっかりついてくるのよ!!」と、必ず子どもに熱心に伝えた上で、子どもがよそ見をしている時に迷子にしてあげる。とか、、
「お母さんは手荷物がいっぱいで手を繋いであげられないけど、しっかりついてくるのよ!!」と言って人混みの中で手を繋がずについて来させる。
等々。。。
上記のことは5年前にスペインに行き、先日イギリスに行った時から感じていることです。
スペインでは、2歳くらいのよちよち歩きの子が、手を叩くお母さんに向かって一生懸命歩いている最中に、転んで石畳に顔をぶつけました。
それなのにお母さんはどうしたかと言うと、、
そんな光景を微笑ましそうにニコニコ微笑みながら、手を叩き続けていました。
そしたら、赤ちゃんはどうしたかと言うと、、、
転んで一瞬泣いたものの、ニコニコ嬉しそうに微笑むお母さんの顔を見て、直ぐに笑顔を取り戻して、もう一度立ち上がって歩いて行きました。
そしてお母さんのところに来た時に、お母さんはめちゃくちゃ褒めてあげて何回もキスしてあげていました。
あぁ〜〜、これだなぁ〜と、、、日本との違いはこういうところから出てるんだなぁと思いました。
日本ではほとんどの多くが間違いなく、
転んだ瞬間に親が真っ青な顔をして手を差し伸べてしまうと思います。
そして、子どもに頑張らせることすらさせる前に、
子どもが自分の力で立ち上がる機会すら与える前に、
「痛かったねぇ、、大丈夫、大丈夫、、」
なでなで、なでなで、、、
だと思います。
これでは、
「潜在能力を引き出す」どころか、
「自立」するどころか、
「自分の力を自分で出すことのできない『甘えん坊』」
になっていくと思います。
よく次男や三男が長男に比べ少し逞しかったりするのは、段々とこういう部分に手を掛けなくなっていくからだと思います。
ですので、一人っ子に対しても、長男に対しても、次男、三男に対しても、潜在能力を引き出す接し方を意識して取り組んであげるべきだと思います。
先日のイギリスで感じたことは、小松さんと一緒に街を歩いてると、小松さんと僕は一緒にランニングしたり、歩いて遠くまで行ったりしていて、とても歩くのが速い方で、この日も意識して早歩きをしていました。
それなのに、前にいる小学4-6年生くらいの男の子と、中学生の女の子と両親の4人家族にいつまで経っても距離が縮まらないことに気づきました。
「相当早く歩いてますね、、小学生の男の子と、中学生の女の子がいるのに、距離が縮まらないなんて、、」
そんな会話から、、たくさんの例や仮説を聞きながら、、
外国では、赤ちゃんの時から寝室が別で、その結果自立を促しやすいんじゃないか?それなのに愛情は恐らく日本より伝わっているだろう。みたいな話や、色んな話を教育学部の准教授と分析をしながら話しました。
結果、僕が感じたのは、小さい時から子どもに合わせるのではなく、子どもを鍛えるために、子どもの潜在能力を発揮するためにも、子どものギリギリの力を引き出そうとしてあげる教育、接し方が違うのだと思いました。
そして、その結果スポーツの中でも違いが生まれてきているのだと感じました。
恐らく子どもは最初はいっぱいいっぱいだと思います。
遅れてしまう、置いてかれてしまう、、と心配しながら冷や汗もかくだろうし、汗もびっしょりかくと思います。
だけど、そんなギリギリの時に子どもは成長していくのだと思います。
子どもの潜在能力を引き出せる時ってそういときなんだと思います。
『ヤバイ!!!!(冷汗)』
って、本気で子どもが感じてる時に、、
頭をフル回転させて、
全身の力を最大限フルに使って、
持っている本当の力を全て発揮してくるんだと思います。
そういう日常の積み重ねが、
自立したり、
持っている力を全て自分の力で出せたり、
自信を持っていたり、
困ったことを自分の力で解決できたりすることに繋がってくると思います。
みなさんのお子さんにはそういう経験をたくさんさせてあげていますか??
力はあるのに、
『自分の持っている力を自分で発揮できない選手』
『困った時に自分の力で解決できない選手』
『危険なことが分かっていない選手』
が、当クラブにはまだまだいます。
今、最も重要視している課題です。
これに関しては、クラブで出来ることもありますが、日常から各ご家庭で意識して取り組んでいただくしかございません。
もちろん、クラブが、僕達指導者がどうにかしてあげられることもあると思いますので、日々模索しています。
ですが、各ご家庭でももっともっと本気になっていただかないと、子どもの本当の成長は見込めません。
『クラブに預けとけばなんとかなる』という考えではなんとかなりません!!!!
そういった印象を持つご家庭もとても多いです。
クラブで関われる時間は僅かな時間で、みんなが同じ練習をしていて、その中でも成長の差が大きく出ています。
クラブ内で成長の差が出ていますが、他の選手に差をつけている選手は、何が違うのか??親ももっともっと本気になって考えるべきだと思います。
子どもとクラブに任せて放ったらかしでも良いのかも知れません。
けど、今成長してほしい、試合で活躍して良い経験を積んでほしい、と願うなら、子どもとクラブに任せっきりよりも、親も良く考えて本気になって力強くサポートしていくことが必要だと思います。
そして、当クラブ内でもそういう親子が、試合で力を発揮できていることにもっと目を向けるべきだと思います。
活躍しているなりの理由が必ずあります。
3年生で新しく入ってきて、4年生の試合に出てもとても活躍しているA君のお父さんに聞くと、2年生の時から体幹トレーニングを毎日1種類からさせ始めて、今ではお父さんがやらせなくても毎日8種類の体幹トレーニングを欠かさず行っているようです。
また、食事にも相当意識をされていて、小さいころから意識して取り組んできた食事の成果が3年生の現時点で既に大きな成果として出ていると言えます。
自分のお子さんが本当に潜在能力を、「自分の力で発揮できているか?」よく見てみてください。
力を出せていないと感じるのであれば、ご家庭でももっともっと本気になって取り組んでいただくことが、子どもの本当の成長を促します。
クラブでも僕達指導者も、模索していきます。
保護者-選手-クラブ(指導者)が、三位一体となって、本当に力強い子どもの育成をしていくことが必須です。
2017年02月27日
週刊長野にご掲載頂きました!

週刊長野様の『若人の広場』にご掲載頂きました。
身が引き締まる思いです!
引き続き、子ども達が夢を叶える力をもてるように環境を創っていきます。
週刊長野様どうもありがとうございました。
2017年02月27日
スペイン遠征8日目
スペイン遠征8日目

今日は午前中はサンクガットコーチのクリニック
内容は、オフェンス
1、認知
2、前線の選手のプレッシャーのある中でのボールの受け方
3、トランジション
いつもやっているような内容の確認と、より細かい、立ち位置、観るタイミング、速さ、体の向き、をいつもより丁寧に細かくTRしました。
何にしても、強くタフな意欲ある激しいDFの中で攻撃のTRもやらないと意味がありません。
先ずは、意欲的な迫力のあるDFからやりましょう。
その中での、攻撃の技術です。
午前中のクリニックを終わった時点での、Aチームの監督ジョアンは、ジョンソンならサンクガットのAチームでもレギュラーで試合に出ることになる。彼はポテンシャル、パーソナリティーが高い上に、吸収力がとても早く、言ったことが直ぐにできるようになる。
と、とても高く素晴らしい評価を受けました。
午後の休憩は、サンクガットの街中を散策。





みんな最初は同じ場所にずぅーっといて全く冒険しようとしません。
2人組を作らせて、2人組以上にならないようにして、街中を散策させました。
サッカー選手のカードセットを9セットも買った選手が何人かいました。笑
ジョンソンは搾りたての超美味しいオレンジジュースを2パックと美味しいパンを買って、とても良い買い物をしていました⭐︎
帰りはカフェで、一人ずつレジで注文して、買ったものをみんなで食べました。
ジュースやアイスを注文して普通に買って食べることができました。
夕方からは、サンクガット アレビンA(5年生と早生まれ6年生)のCチームと試合を行いました。
この試合では2日間指導をしてくれた、サンクガット アレビンAのAチームの監督ジョアンに試合の指揮も取ってもらうことになりました。
基本的な1-3-2-1の動き方、守り方、戦い方、試合へ向けたメンタル等を指導してくれました。
結果
25分×2本
10分×1本
2-7●
(ハル、ジョンソン)
立ち上がりや、メンバー、時間帯、システムによって、流れが変わり、かなり優勢な時間帯から押し込まれる苦しい時間帯がありました。
それでも立ち上がりと、後半の途中からは互角以上の戦いをしていて、明日の大会に向けてはとても期待の持てる内容となりました。
明日はいよいよ大会です。
とりあえずカタルーニャの強豪チーム達と言われている街クラブから勝利を上げて準決勝進出して、バルサだけでなくエスパニョールと試合することを目指して戦います。
明日の試合が楽しみです!!



今日は午前中はサンクガットコーチのクリニック
内容は、オフェンス
1、認知
2、前線の選手のプレッシャーのある中でのボールの受け方
3、トランジション
いつもやっているような内容の確認と、より細かい、立ち位置、観るタイミング、速さ、体の向き、をいつもより丁寧に細かくTRしました。
何にしても、強くタフな意欲ある激しいDFの中で攻撃のTRもやらないと意味がありません。
先ずは、意欲的な迫力のあるDFからやりましょう。
その中での、攻撃の技術です。
午前中のクリニックを終わった時点での、Aチームの監督ジョアンは、ジョンソンならサンクガットのAチームでもレギュラーで試合に出ることになる。彼はポテンシャル、パーソナリティーが高い上に、吸収力がとても早く、言ったことが直ぐにできるようになる。
と、とても高く素晴らしい評価を受けました。
午後の休憩は、サンクガットの街中を散策。





みんな最初は同じ場所にずぅーっといて全く冒険しようとしません。
2人組を作らせて、2人組以上にならないようにして、街中を散策させました。
サッカー選手のカードセットを9セットも買った選手が何人かいました。笑
ジョンソンは搾りたての超美味しいオレンジジュースを2パックと美味しいパンを買って、とても良い買い物をしていました⭐︎
帰りはカフェで、一人ずつレジで注文して、買ったものをみんなで食べました。
ジュースやアイスを注文して普通に買って食べることができました。
夕方からは、サンクガット アレビンA(5年生と早生まれ6年生)のCチームと試合を行いました。
この試合では2日間指導をしてくれた、サンクガット アレビンAのAチームの監督ジョアンに試合の指揮も取ってもらうことになりました。
基本的な1-3-2-1の動き方、守り方、戦い方、試合へ向けたメンタル等を指導してくれました。
結果
25分×2本
10分×1本
2-7●
(ハル、ジョンソン)
立ち上がりや、メンバー、時間帯、システムによって、流れが変わり、かなり優勢な時間帯から押し込まれる苦しい時間帯がありました。
それでも立ち上がりと、後半の途中からは互角以上の戦いをしていて、明日の大会に向けてはとても期待の持てる内容となりました。
明日はいよいよ大会です。
とりあえずカタルーニャの強豪チーム達と言われている街クラブから勝利を上げて準決勝進出して、バルサだけでなくエスパニョールと試合することを目指して戦います。
明日の試合が楽しみです!!


2017年02月27日
スペイン遠征7日目[サンクガットクリニック&ミラソルTM]

7日目は午前はサンクガットクリニック、サンクガット アレビンAのトップチームの監督が、初日の合同TRを見て、大会に向けて必要なことをTRしてくれました。
サンクガット アレビンAの監督はバルサとリーグ戦で0-1の接戦の試合をした優秀な監督だと讃えられていました。
(サンクガットの大会では、サンクガットBが予選でバルサに1-0で勝ちました。)
内容は、ほぼDF。
DFの球際をもっともっと強くする必要があると。
DFの個人戦術からグループ戦術までを、もの凄く情熱的に熱く伝えてくれました。
1対1の方法とグループで守る方法をやりましたが、
何よりも重視していたのは、『執着心』でした。
もっとボールを守れ!!と、
もっとボールを必死で奪いに行け!!と。
物凄い気持ちと情熱を持って伝えてくれたので、少しずつ変化していきました。









午後は、サンクガットの地域のミラソルというチームとTMでした。
ここには6-1,5-0で勝ちました。
帰りはグラウンドから約5KMの道のりを探検しながら走って帰りました。



2017年02月26日
スペイン遠征6日目[サンクガット合同TR]








今日はSant Cugat(サンクガット)との合同TRです。
サンクガットはカタルーニャ州1部リーグに同じカテゴリーでも複数チームが所属し、バルサやエスパショールと試合を重ねている強豪チームです。
先ずは、3人×3グループ+GK1人に分けられ、サンクガットの複数チームに割り振られます。
サンクガットは同じベンハミン(5年生+早生まれの6年生)のカテゴリーでもA,B,C,Dの4チームに分けられています。
そして、ロッカールームでミーティングから始まり、グラウンドに出てTRが始まります。
ローッカールームでの盛り上がった様子や緊張した様子、チュン...となっている様子、TRの様子は写真ではとてももったいないので全部動画に撮ってあります。
今日の合同TRは、W-UP数種類の後、全部紅白戦でした。
スペイン人の中に入って試合をするのは、とても良い経験になりました。
ボールを前に運ぶ、突破する、チャンスを作る、シュートを打つ、ゴールを決める、相手からボールを奪う、奪われたボールを直ぐに奪い返す、、
サッカーの中での『仕事』をしているのは全てスペイン人でした。
日本人は、ボールをもらう(そもそもボールをもらえない、ボールに触れない選手も複数)直ぐに返す or 奪われる or 横か後ろに運ぶ→横か後ろにパス、
プレッシャーに素早く寄せる、、だけで、身体でコンタクトせずに奪えずない、、
早く寄せるけどぶつからないのでプレッシャーになはならず、ボールを奪ってくれるのは全てスペイン人、、
サッカーの仕事をするのも全てスペイン人といった情けない結果になりました。
8人制の試合をして日本人が3人固まったチームが最下位になりました...
日本人が2人かわされ失点した後、怒ったサイドバックのスペイン人が、日本MF3枚を無視して一人でドリブルで中央突破からロングシュートで決めたゴールは圧巻でした!
『フザケンナよ!!お前らのせいで俺は負けたくねぇーんだよ!!俺が一人で点取ってやる!!!!!!』
といった気持ちをプレーで見せ付けられました。
練習が終わったあとその話をみんなにしたら、同じチームだったユウマが泣いて「けど、あいつは全然DFをしてくれなかった」と言っていました。
ボールを奪うのもスペイン人、前に運ぶのも、シュートを打つのも、チャンスを作るのもスパイン人、、
もっと『サッカーの仕事をする!!』『結果を出す!!』というところに執念と執着を持ってプレーしてください!!
他の試合では、チームサンクガットに日本人とスパイン人のハーフの選手がいました。
見た目はほぼ日本人で日本語も話せます。
だけどプレーは、『ライオン』のその子と『子猫』のノザワナ選手達くらいの迫力と意欲で、超目立ってました。
半分は日本人です。でもそれくらい目立つんです。
左サイドバックでプレーしていましたが、その一つ前のポジションには同じプレースタイルで同じ左利きのハルが左サイドハーフをやっていました。
その意欲と迫力で、ノザワナでは攻撃の中心のハルも全部喰われて、目立つところ『サイドでの仕事』を全て持っていかれていました。
やっぱりサッカーの中で、試合の中で、『自分の役割』『仕事』を行うことがどれだけ大切か、、
『役割』『仕事』ができないということは、どういう評価を受けるか、、
『自分の役割』『自分の仕事』を他の人に取られてしまう、、ということがサッカーの中で、社会の中で、
何を意味しているということなのか。。。
よく考えて欲しいと思います。
そして、忘れないでください。
その『意欲』と『迫力』によって、のし上がっていくパワーを。
2017年02月24日
スペイン遠征5日目[バレンシア観光&レバンテクリニック&座学]

スペイン遠征5日目の今日はバレンシア観光→パエリア発祥の地で本場パエリア→レバンテクリニック2日目&座学です。
バレンシア観光は、リガーエスパニョーラの名門バレンシアCFのホームスタジアム「メスタージャ」、バレンシアショップ、バレンシア市内観光です。



そしてホテルに帰って、本場の手作りの20人前のパエリアです。
本場のパエリアにはうさぎの肉が入っているようです。



にんにくマヨネーズのポテトもお店で出るやつよりはるかに美味しいようです

アボガドとトマトのディップも手作りで、とても美味しかったです

サラダ

こんなに大盛りでも美味しくて、みんな食べてました
アテンドしてくれているスペインに7年在住している神倉さんも、今まで食べたパエリアの中で1番美味しかったそうです。
午後は、レバンテクリニック2日目です。
昨日のTMをビデオで分析して必要なことをやってくれました。
1、ポジションチェンジでマークを外す
2、サイドで意図的に数的優位を作る方法
3、トランジション&数的優位の活かし方、突破の方法
エイトは今日も評価がとても高く、トレーニングを終えたキーパーコーチ達が、レバンテで契約した方が良い、と話しをしていたと聞きました。
そして、座学では、昨日の試合の映像を編集して、
レバンテのシステムの変化と、
それぞれに対する攻略方法と気をつけるべき点、
ノザワナのシステムの弱点と長所、
上手くいった良い例と、やられてしまった悪い例
等々を昨日の試合映像を編集して解り易く説明してくれました。
衝撃的だったのは、こちらのプレスを外す方法を緻密に意図的に行われていたこと。
戦術的に、意図を持って狙い通りにプレスを外され、チャンスを作られていました。
マークしていたボランチはとても迷わされて、他のポジションの選手も相手の意図に乗っかってしまった形でキレイに崩されてしまいました。
あとは、ボランチとFWがマンツーマンで来た時のマークの外し方がとても上手かったことに驚きました。
マンツーマンからのマークの受け渡しを引き出す動きからフリーになる動きで、マンツーマンしてたにも関わらずキレイに外されてボールを意図的に受けられていました。


2日間を終えて評価が高かったのは、ジョンソン、ユウマ、エイトでした。
元FCバルセロナの育成部門のコーディネーターをしていた、育成部門のディレクターダニエルさんは、ユウマとジョンソンのレベルであれば、スペインにいればかなり高いレベルのチームと契約できると言われていました。
スペイン人であればレバンテで契約することもできると言われていました。
レバンテはバレンシア州では、バレンシアとビジャレアルの次にくるチームです。
エイトは、チームでは3番目に評価が高く、「才能はあるけど、まだキーパーを初めたばかりだから、何回か練習に参加すれば君も可能性は高い」と言われていました。
是非、スペインに残って可能性を高めてください。
2017年02月22日
スペイン遠征4日目[レバンテクリニック&TM]
Hola!! buenos dias!
スペイン遠征4日目、レバンテクリニック&TM

レバンテクリニックでは、送ってあるビデオに対して分析し、TRを行ってくれました。
内容は初日は、
1、ポジションでのレバンテが考えるボールの動かし方と人の動き方、ビルドアップ
2、突破の方法(サイドから数的優位を作る方法)
3、ビルドアップからFWの活かし方(FWの受け方)
4、ゾーンを意識した突破の仕方
と、通常では有り得ない盛りだくさんのテーマで、一つずつの意識付けを目的に行われました。
子ども達の様子はというと、、
やっとサッカーが始まったということもあり、意気込んで大分息が上がって疲れていました。
初日のクリニックで1番評価が高く、褒められた選手はエイトでした。
今のレアル・マドリードのGKナバスを15歳〜プロになるまで育成したコーチに、「こいつは何者なんだ!すごい吸収速度だ!!才能がある!!」ってベタ褒めされていました。
午後はいよいよレバンテ(2006年生まれ)とのトレーニングマッチ
(学年でいうと4年生と早生まれの5年生)
こちらは、2005年生まれが3人、あとは全員2006年生まれと、ほぼ同学年との試合となりました。
※大会は2005年生まれの大会に出ます。。笑(5年生と早生まれの6年生)
体格は4年生とは思えないほどのデカさでした。。
8人制
12分4ピリオド予定が、なかなか健闘したため、5ピリオド目もやろう!戦術的にも君たちにもっと見せたいものがある、と提案をいただいて全部で5ピリオドやりました。
・1P(前半)
0−0
・2P(前半)
0−2●
・3P(後半)
0−4
・4P(後半)
0−4●
・5P
1−0○
(ジョンソン)
合計1−10●
相手は、こちらに数種類の戦い方を見せたいと、1P,2Pと5Pを本来の戦い方、3P,4Pを特別な戦術と、使い分けて試合をしてくれました。
1,2,5Pに関しては、手応えを感じた内容となり、自信を付けた選手も多かったです。
もちろん3,4Pのメンバーにも自分のできることは出せた!と、手応えを感じている選手もいました。
反対に、課題を感じた選手も多くいました。
4日目のレバンテクリニック&TMは取り急ぎこんな感じです。
スペイン遠征4日目、レバンテクリニック&TM

レバンテクリニックでは、送ってあるビデオに対して分析し、TRを行ってくれました。
内容は初日は、
1、ポジションでのレバンテが考えるボールの動かし方と人の動き方、ビルドアップ
2、突破の方法(サイドから数的優位を作る方法)
3、ビルドアップからFWの活かし方(FWの受け方)
4、ゾーンを意識した突破の仕方
と、通常では有り得ない盛りだくさんのテーマで、一つずつの意識付けを目的に行われました。
子ども達の様子はというと、、
やっとサッカーが始まったということもあり、意気込んで大分息が上がって疲れていました。
初日のクリニックで1番評価が高く、褒められた選手はエイトでした。
今のレアル・マドリードのGKナバスを15歳〜プロになるまで育成したコーチに、「こいつは何者なんだ!すごい吸収速度だ!!才能がある!!」ってベタ褒めされていました。
午後はいよいよレバンテ(2006年生まれ)とのトレーニングマッチ
(学年でいうと4年生と早生まれの5年生)
こちらは、2005年生まれが3人、あとは全員2006年生まれと、ほぼ同学年との試合となりました。
※大会は2005年生まれの大会に出ます。。笑(5年生と早生まれの6年生)
体格は4年生とは思えないほどのデカさでした。。
8人制
12分4ピリオド予定が、なかなか健闘したため、5ピリオド目もやろう!戦術的にも君たちにもっと見せたいものがある、と提案をいただいて全部で5ピリオドやりました。
・1P(前半)
0−0
・2P(前半)
0−2●
・3P(後半)
0−4
・4P(後半)
0−4●
・5P
1−0○
(ジョンソン)
合計1−10●
相手は、こちらに数種類の戦い方を見せたいと、1P,2Pと5Pを本来の戦い方、3P,4Pを特別な戦術と、使い分けて試合をしてくれました。
1,2,5Pに関しては、手応えを感じた内容となり、自信を付けた選手も多かったです。
もちろん3,4Pのメンバーにも自分のできることは出せた!と、手応えを感じている選手もいました。
反対に、課題を感じた選手も多くいました。
4日目のレバンテクリニック&TMは取り急ぎこんな感じです。
2017年02月20日
スペイン遠征3日目
最初の2日間はサッカー観光的な部分が多かったですが、今日からはやっと本格的なサッカーが始まります。
今日はリーガエスパニョーラ レバンテでのクリックとトレーニングマッチです。
やっと、サッカーが始まります!!
今日はリーガエスパニョーラ レバンテでのクリックとトレーニングマッチです。
やっと、サッカーが始まります!!

2017年02月20日
カンプノウでバルサ戦観戦




カンプノウでバルサ対レガネス戦の観戦。
立ち上がり3分にメッシがゴールを決めて盛り上がりました。
バルサの内容はファンタスティックではありませんでしたが、、レガネスが追い付いて、最後にイニエスタ、ジョルディアルバ、デニススアレスが出てきて、意図的に攻撃の方法が変わり、相手を押し込みはじめて、ネイマールがPKもらって、メッシ2点目という、試合展開は劇的でした。
他の写真はFacebookに貼ってあります。
見てみてください。
https://www.facebook.com/nozawanafc/posts/1446154188749315